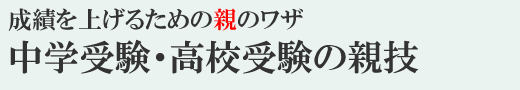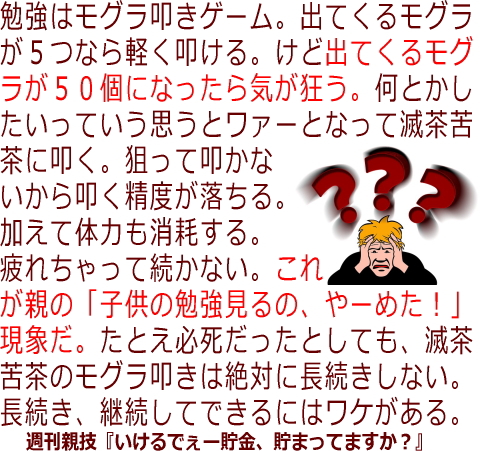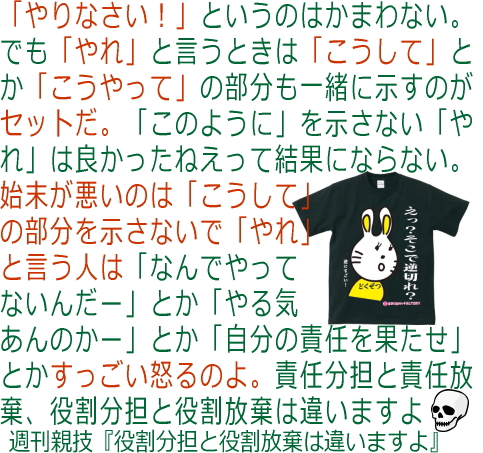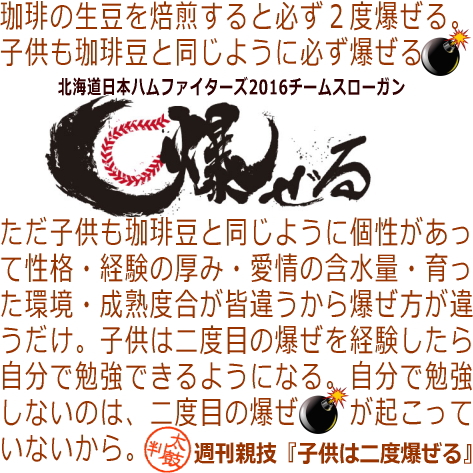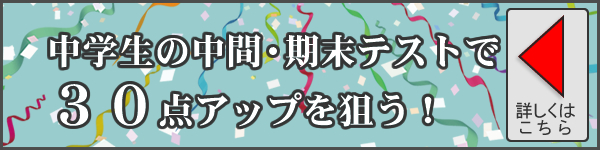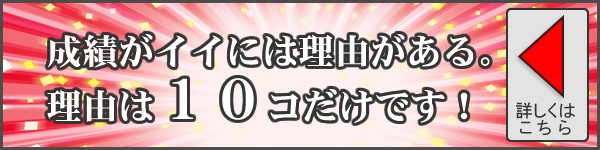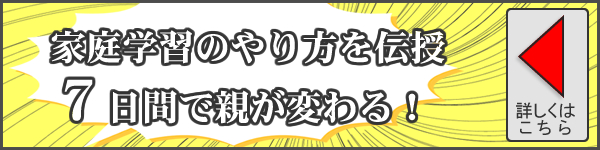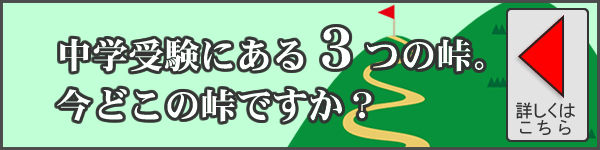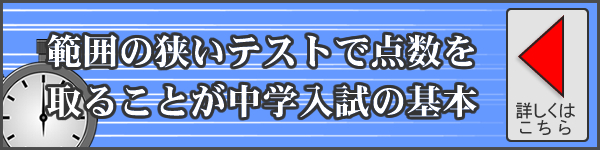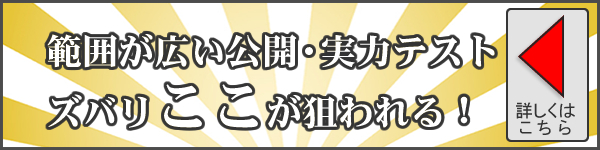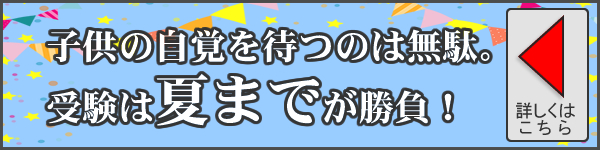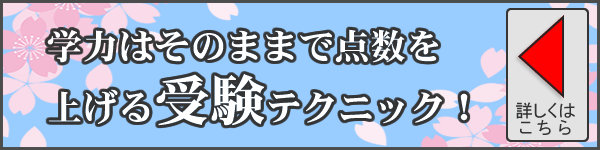こんにちは、ストロング宮迫@親技.comです。
もう11月の中旬ですか。。。早いねえ。今年もあと1ヵ月半ですか。頑張ってしっかり子供の勉強を見ていきましょう!
さて、今回は2つほどメールを紹介します。
いずれも子供に「なにやっているんだ」という刃を向けるのではなく、親自身が「なにをやってきたのか」と親自身に対して刃を向けている方、つまり親にとって最も困難な作業に今現在着手されている方のメールです。
親は、基本的に誰からも怒られることなく、また強制されることがないため、子供を観察して、自分で考えて、自分で検証しなければならず、よって世の中の仕事の中では最も難しい仕事のうちの1つであるとボクは思っています。
みんな我が子については、平等に「創業者」だから「創業者並み」の苦労がある。ただ親の場合は、自分で考えて問うという作業を別にしなくても、誰からもクレームはきません。まさに唯我独尊の立場にあるのが親ってわけですね。
ああ、クレームはくるか、子供からだけは。
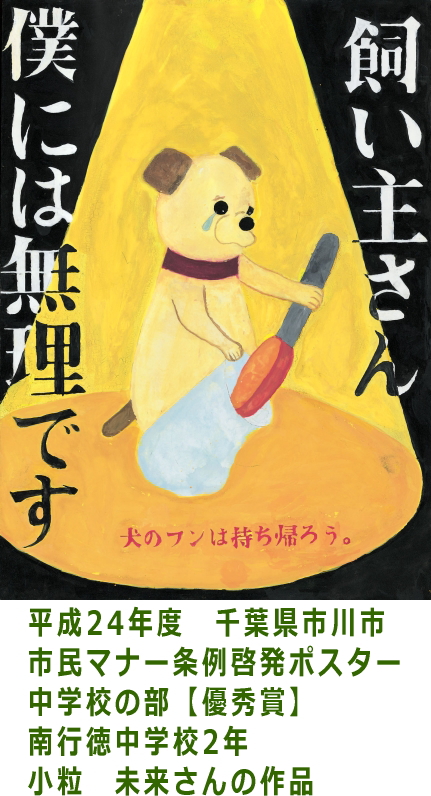
でも、子供からのクレームなので「お前(子供)が悪い」と、いわゆるクレーマーからの苦情として処理することが親には可能です。それで誰にも迷惑はかからない。
まあ、子供にとっては迷惑なんですがね。
そんな最も難しい「自分を問う」作業を自らやり遂げようとされている方からのメールです。
あなたは、この終わりなき戦いの火中の栗を拾えるか。選択は自由です。
親がもらえるご褒美は、「たったの」子供のキラキラした表情だけなので、そこに100万ドルの価値を見出すか、1ドルしか見いだせないかで、選択は変わってくる。
どう考えるかはあなた次第ですし、どうしようが文句はありません!
Let’s Go!
小5 トンビさん
復テの成果が出ました。
ストロング宮迫先生、お世話になります。週刊親技「いけるでぇー貯金、貯まってますか?」でアドバイスいただいたトンビです。
今秋から始めたいけドンシートのおかげで復習テスト科目合計、偏差値62となりました。
52→48→62となり、親としてようやく、成果につながるやり方にたどり着けたと安堵しましました。
B・C問題は捨てるというより、手が回らず例題をA問題としてやりました。
悪く出ても仕方ない今回は初回なので、いけドンシートを試そうと。その為、私自身結果を受け入れるにも複雑でした。
それと言うのも、今回は急いで始めたもので、『10の鉄則』の復習もせずバトル勃発。
己への刃があろうことか、我が子へ向きかけたり…。
よくよく考えれば、いままで、子供の頭の上に応用という皿を、まだ乗るまだ乗る、早くこれも乗せないと届かないのよ!と乗せすぎて、落とす。そして、なぜ落とすの、しっかり見て乗せたの、しっかりしなさいと…。
違ったのですね。
子供の足元に一つずつ基本の石を積み上げ「いけるか~、ぐらつなかいか~」大丈夫だったら、もう一つ積んでみようかと乗せてやらねばならなかったのですね。
親技を少し理解できました。
しかし、まだ今回はデタラメで、丁寧に時間を計れていない。繰り返しも雑。問題選択も課題。解き方は時短か。テストの受け方もまだ今まで通り。カイゼンの余地はたっぷりです。
成果を出しても逆戻りもあるとありましたので、私自身が親技偏差値をあげる努力をしながら、子供の伴走がうまくできるよう努力していきます。
長々とすみません、つい、ほっとして気がゆるんでしまったので、ご報告させていただくことで、休んではならないやるのだぞと気を引き締めさせていただきました。
いつも、ご指導ありがとうございます。
模擬テストの結果はまだです。公開対策は間に合わなかったので、前回の問題をみたり、過去問をしたのみでした。また、ご報告できるよう、いけドンシートを用意していきたいと思います。
いかがでしょう?
よくよく考えれば、いままで、子供の頭の上に応用という皿を、まだ乗るまだ乗る、早くこれも乗せないと届かないのよ!と乗せすぎて、落とす。そして、なぜ落とすの、しっかり見て乗せたの、しっかりしなさいと…。
この誰もが必ず通る道を通って、そしてこの心境にたどり着くまでに親は多くの時間を費やし、子供を傷つけ、回り道をします。
自分に刃を向けているつもりでも、意識して自制しなければ、つい子供に刃を向けてしまっていた・・・なんてことは親技を駆使しようとする者にはよく起こります。
「ほっとして気がゆるんでしまった」なんてことも多々あることで、それでも親は、すでに書いたように「創業者」であり、家庭内の「ワンマン社長」なので、そうしたとしても誰も指摘はしないし、咎めもしない。
勉強面でいえば、成績にそのやったことが反映されるだけです。
友達の親に聞いても「あなたが悪いのよ」なんて言われることはなく、「ウチも一緒よ」って相槌をうたれるのが関の山。子育てに関しては、親はいつも孤独だ。
常に出てきた結果や現象を見て、その結果から自分が子供にしてきたことの意味を探るしかない。
正しかったのか正しくなかったのか。
伝わったのか伝わっていなかったのか。
やりすぎが、適正か、少なすぎか。
難しすぎか、適正か、易しすぎか。
ノリノリか、普通か、無反応か。
前向きか、ボンヤリか、後ろ向きか。
答えはすべて目の前の子供に出てる。あとはそれを受け入れるか、受け入れないか、なかったことにして知らんぷりするか。あなた次第だ。
なりたくて「創業者」や「ワンマン社長」になったわけではないんだけどね・・・ゆえに親の子育ては、世の中でももっとも難しい職業の1つといえるんじゃないか。
この前、家に帰ってテレビをつけたら、ちょうど生まれたばかりの我が子を抱えたタレントさんが映っていて、字幕に「ついに父親になった」というのが出ているのを見ました。
バラエティー番組にケチをつけるつもりはないので、それはいいとして、ボクの感覚では、初めて子供を抱いても、男性は「父親にはならない」とボクは感じています。
女性は「子供を産む」という過程を経て、身をもって「母親にはなる」でしょう。
でもね、父親は自動的に「父親」にはならないし、なれない。だから、戸籍上は父親でも、子供が中学生くらいに成長していたとしても、「まだ父親になっていない」男性は世の中にたくさんいるとボクは想定しています。
父と名乗ることは許されるけれど、子供に接して慈しんで初めて「父親」のようなものになった気がして、思い通りにもならず、悪いところばかりそっくりになった事実を真正面から受け止めたとき、初めて「父親になる」。
振り返ってみると、ボクが第一子の長男坊の「父親になった」のは、恥ずかしながら、小学校の3年か4年か、10歳になろうとしていた頃だったと思える。
それまでボクは「父親ごっこ」をしてただけだ。それまでは「なんちゃって父ちゃん」で、父親のような、親のようなフリを、形としてしていただけ。形の上では「父親になった」からといって、すぐに「父親」にも「真っ当な親」にはなれない。
・・・というようなことを考え始めて、初めて「父になる」んじゃなかろうか。
加えて、ボクらは、正しいことがなにかとわかっていても、すぐにできないことが多い。
子供のせいではなく、親である自分の問題ではないかと「問えばイイ」ことはわかっていても、なかなかこれができないんだな。できないで3年くらいは、すぐ経つ。
できなくても、誰からも問われないので、会社みたいに倒産や破産という事象には表れないで、そのまま何事もなかったようにいってしまう。いずれその代償は蓄積された分、どこかで払うことになると思うけれど。
向き合って「わかる」から、もう一歩先の「わかったことをできる」は果てしない壁があるのかもしれない。すぐ越えられる人もいれば、一生越えられない人もいる。
ただ壁の高さはおおむねみんな同じ設定になってる。だから平等。「わかって、それができる」が達成できないと、壁際をずっと走ってクリアできずに子育て卒業ってことになる。つまり「わからなかった」ってことだから来世でもう1回やり直しだ。
もう1つのメールは、「すでに父親になって」久しい方からのメールです。あとで触れるのに便利なように途中でボクが勝手に番号を振っていますが、気にせずお読みください。
生物大好きっ子さん
小学3年生の子供の父親です。
4月から子供と二人親技に取り組んでいます。以前、週刊親技「役割分担と役割放棄は違いますよ」でご紹介いただきありがとうございました。
先日の週刊親技「子供は二度爆ぜる」を拝見し、先生からの【問い】を考えてみました。
我が子は小学2年から大手受験塾に通塾を開始、クラスは下から2番目でした。
塾の宿題は一人でやらせるものの、半泣き状態で取り組む有様。とりあえず形だけになり、全く理解はできていませんでした。当然テストを受けても結果はでませんでした。
1.この時期はまだ「焙煎」できていなかったんですね。
そんなある日、子供から衝撃の言葉が・・・
「塾の先生が何を言っているかわからない。僕は何でこんなことしているのだろう」
この言葉を受けてこれまで母親任せだった子供の勉強を五時半に起きて「朝勉「と称し、親技をスタートしました。
2.これが、「焙煎」の始まりですね。
それまでは、毎日取り組むべき基礎問題集もやったりやらなかったりでしたが、「どんなことがあっても必ず毎日基礎問題集だけはやる」という【約束】をしました。テキストもA問題を「早く解ける」様になるまで繰り返しました。塾の先生にも電話し、どうやって問題に取り組むべきかも教えてもらいました。
驚くことに「焙煎」を始めると「豆」がチリチリと音を立て始めるのに時間はかかりませんでした。
5月の確認テスト 160点
(体調不良のため受験こそできませんでしたが自宅で取り組み)
最上位クラス基準クリア7月の実力テスト 156点
上から2番目のクラス 最上位クラスにあと4点10月の確認テスト 160点
あと2点及ばず2番目のクラス下から数えた方が早かった子供が全体の上位20%ほどの位置をキープできるようになりました。
さらに驚いたことに「算数1問で人生がかわることもあるんだね」と息子が言ったのです。
3.最近は「塾に行くのが楽しい」とまで言うようになりました。妻とも「最近変わったよね」と話していましたが、我が家ではこれが「1回目の爆ぜ」だったんだと思います。
しかし10月の確認テスト以降、毎日「朝勉」をしているものの、これまでと違い息子の起床時間が10分、15分と遅くなり、明らかにテスト前に比べペースが落ちてきたのです。
4.休日も「朝食のあと勉強する」といっても、結局やりません。
最初は「テストがおわってから油断してるな。まあ仕方ないか。」と思っていましたが、一度緩んだペースは簡単に回復できません。
同じことをしているはずなのに、どうして元のペースに戻せないのか。不覚にも息子をしかることも何回かありました。正直迷いました。これまで順調だっただけに・・・
そこで理解していたはずの10の鉄則をもう一度読み返してみました。するととんでもないことに気づいたんです。
原因は「息子の油断」だと思っていました。息子が悪いんだと・・・
でもそれは間違いだったんです。
明らかに「焙煎」の火加減が弱くなっていた、弱くしたのではなく、気づかないうちに火が弱くなっていた。そう、油断していたのは自分だったんです。
幸いにも「火加減」の変化に早く気づくことができたため、少しずつですが元のペースに戻すことができました。
今回「子供は二度爆ぜる」を拝見し、先生からの【問い】に答えながら自分なりの答えを出しました。
「1度目の爆ぜ」は確かにきついですが、モチベーションも高く何かしら体験することができる。でも「2度目の爆ぜ」まで火加減を良い塩梅に保つのは難しい。
なぜなら「焙煎」の火加減は「自分では弱めているつもりはなくて、いつの間にか弱まっているから。しかも突然「強火」から「弱火」に変わるんじゃなく、「強火よりの中火」「弱火よりの中火」になっているからたちが悪い。
だから時々「焙煎」の火加減が適切かどうかを、親が自ら問う必要がある。
たまには全然乗らない日もある。だから意図的に火を弱める日もあっていい。でもたとえ1日でも火を消してしまったらだめ。だって子供の「焙煎」の火種はスイッチ一つでつくわけではなく、またイチから火をおこさないといけないのだから。
いかがでしょうか?
まだ「2回目の爆ぜ」の音は聞こえてきません。もしかしたら音は出ているのかもしれません。
しっかりと息子の放つ音に耳を傾け続けようと思います。「先生の2回目爆ぜれば、絶対に自分で勉強するようになる」を信じて。
ボクの書いた読むべき義務もない文を読んで、ここまで自分のことに当てはめて消化して吸収して、もうウンコまで出しちゃった生物大好きっ子さん、この行為こそが成績がイイ子の行動原理と言ってもイイでしょう。

イイ授業か、イイ先生か、環境が素晴らしいとかは関係ない。いったん縁があって、目にした耳にした「授業」はすべて消化吸収してウンコを出すまで仕上げてしまう。必要なければもう口にはしないだけ。
意識的か、無意識的かは別にして、勉強で「成績がイイ子」はそうしてる。親技ではそれを無意識ではなく、意識して、言語化して、誰にでもできるようにしたいって思ってる。
どこかの時点で「成績不振」という結果が出て、それを何とか挽回しようって親が考えたとき、たどる経路は生物大好きっ子さんがたどった経路と同じ道を誰もが通ることになります。
「1.この時期はまだ【焙煎】できていなかった」と認識し、焙煎を開始する。焙煎をする前には道具も準備しなきゃいけないし、揃ったとしても、そもそも初めてやる場合は、火加減がわからない。
最初に紹介したトンビさんがそのことを示してくれていて、
よくよく考えれば、いままで、子供の頭の上に応用という皿を、まだ乗るまだ乗る、早くこれも乗せないと届かないのよ!と乗せすぎて、落とす。そして、なぜ落とすの、しっかり見て乗せたの、しっかりしなさいと…。
と、早く「焙煎」を仕上げたいと気持ちがせいて、「豆(子供)の気持ちや事情」を考えず、火加減が強くなりがちだ。だから焦げる。豆は焦げて炭化するけど、子供は反抗するか、暴れるか、泣くという現象でそれが出る。
エラーが出たら、もっと強くしてもダメだ。
戻る。難しいけれど、歯を食いしばって唇から血が出るくらい噛みしめてでも戻らなきゃいけない。
つまり火加減を落とすわけだ。
火加減を落とすには、どうしても「子供が悪い」から親自身が「なにがいけなかったのか」への視点の転向が求められる。
視点が変えられなければ、「ウチの子、アホですから」でジ・エンドになる。やっぱり来世でやり直しだ。解決できなかった課題は何回生まれ変わっても、時を変え、場所を変えて、またその課題が出てくるのが世の常だから。
夏頃にここで「親のあなたへは、この前ボクが見た映画「あん」を宿題として出しておきますので、機会やお時間があればぜひ見てみて下さい」と書いた。
この映画を見ていただくと、火加減の話はよく分かってもらえるんじゃないかと思います。
「豆(子供)の気持ちや事情」、「豆の話や声」「どうしてキミは私のもとに生まれてきたのか」も含めて豆(子供)の声を聞かなきゃ始まらない。
料理はともかく、子供に「強火」は副作用が多すぎるとボクは考えています。ジワジワ、ボツボツやるのが一番。
そしたらね、その熱で温まった「豆(子供)」は熱を帯びて勝手に自分で爆ぜていくから。まあ、たいていは親が爆ぜるまで待てないような時期に入試がくるんだけどね。よくできてるよ、世の中のシステムは。
生物大好きっ子さんのメールに話を戻します。
「そうか、焙煎してなかったんだな」という認識から2.「焙煎」の始まり
生物大好きっ子さんは、ボクと違ってかなり賢い方だから、最初から強火にしないで、火加減を間違わなかった。
「テキストもA問題を早く解ける様になるまで繰り返し」ました。
ボクが最初焙煎したとき、第一子も珈琲豆も火を出して燃えてしまうほどの火加減で煎ってしまった。だから焦げて火事になった。そして、子供に「お前の火の不始末だろ!」って怒ってた。チーン!ですな。

だって火元はボクだからさ。
火事は火元が責めを負わなきゃいけないのに。皆さんには最初から、火加減を間違わずにやっていただきたい。
ポイントは「火の加減はこれくらいですよね?」ってあなたが思っている火力よりも2段階ほど下げてから始めるのがちょうどイイくらいです。最初は火加減も抑えてやることです。
火加減を強くすることはいつでもできる。でも最初から強すぎると副作用が大きくて、後処理がたいへんになるから。
火加減がちょうどいいと、そして継続すると、必ずすぐに1回目の爆ぜが来る。
驚くことに「焙煎」を始めると「豆」がチリチリと音を立て始めるのに時間はかかりませんでした。
3ヵ月たってもチリチリと音がしない場合は、火加減がたいていは強すぎるはずです。
1回目の爆ぜ「1ハゼ」が起こると、「子供が全体の上位20%ほどの位置をキープできるように」なるのもその通りだと思う。
ただ学年が上がれば上がるほど「1ハゼ」で上位20%に入れる確率は低くなっていくことは覚えていてほしい。たとえば「1ハゼ」を知らずに高校生になると、もう勉強における「ハゼ」は、ほぼ起こらない。起こることはもちろんあるけれど、奇跡と呼べる確率になってしまう。
だからできるだけ早く「焙煎」を始めることです。早ければ早いほどすぐ結果が出るし、「1ハゼ」で上位20%に入れる。
1000人いれば200番
300人いれば60番
200人なら40番
100人なら20番だ
親の手を借りながらでも、火加減と継続でここまではいける、そのことを生物大好きっ子さんは証明してくれているんじゃないでしょうかね。あなたにも同じことが起きるし、起こせる。視点さえ変えられれば、それを実行できれば・・・
子供に特別な才能がなくても、この枠にはみんな必ず入れるってボクは確信しています。そのためには「焙煎」しなきゃいけないし、1ハゼまでは起こさないといけないが。
この1ハゼが起こる前には必ず前兆がある。言動や行動、表情もそうだけど、どこかで親がこんなことを思ってたのかと思うような「ビックリする」ことが起こる。そのことも生物大好きっ子さんのメールには記されてる。
3.最近は「塾に行くのが楽しい」とまで言うようになりました。妻とも「最近変わったよね」と話していましたが、我が家ではこれが「1回目の爆ぜ」だったんだと思います。
この変化に気づかない人もいて、見逃せば、数度見逃せば、子供は親に仮に化学変化を起こしていても、その変化を見せなくなる。
また、1ハゼは、1回爆発がバーーンと起こって終わりじゃない。珈琲豆は装置や火加減や豆の量にもよるんだろうけれど、1分半から2分ほどは1ハゼの状態が続きます。
生物大好きっ子さんでいえば、
5月の確認テスト 160点
7月の実力テスト 156点
10月の確認テスト 160点
このあたりが1ハゼが続いている状態なのかもしれませんね。たぶんそうだ。
そして静寂が訪れる。1ハゼが終わって、次に2ハゼが起こるまでの1分くらいの間、あのパチパチは何だったのか?ってくらいの静寂だ。耳を澄ませば、なんだか音も聞こえるけれど、1ハゼの賑やかな音に比べれば、静かだ。
そ「1ハゼの後の静寂」それがこの↓↓↓4番目の段階じゃなかろうか。
4.休日も「朝食のあと勉強する」といっても、結局やりません。
生物大好きっ子さんでいえば、子供は「160点」を獲るための勉強量も、なにをやるべきかもわかってきた。どうすべきかも、だいたいわかってる。
だけど、身体が動かないんだな。大人でもあるでしょ?
期限までは1週間!しかし、動き出すのは前日からとかさ。ホントは1週間前から徐々に少しずつやればいいんだけど、子供も大人もこれが難しい・・・
でも前日からやっても仕上がるの。どうすべきかも、なにをすべきかもわかってる人がやればさ。これを帳尻合わせという。
まあ、だいたいいつも通り仕上がるけれど、もうちょっとやりようがあったんじゃない?って感じです。
もし、1ハゼが起こってない状態で、この「前日仕上げ」をしようとすると、すごく無駄が多くなる。余計なことをしたり、難しいことをしすぎたりさ。
そもそも「どうすべきか」「なにをすべきか」がわかっていないので無駄が多くなるのは必然だ。この段階の子供だと、頑張った分量の半分しか成果には反映されない。100点目指してて頑張ったのに50点を獲ってくる感じです。
多くの人がここに留まってる。「1ハゼ」を起こすのが先決なのに「ただ頑張る」「無闇に頑張る」「必死にやったんだが・・・」がこの段階の人たちを表す。
でも1ハゼが起こって、成果も複数回出て、どうすべきかがわかってると、わかっているからこそ、緩むという問題も出てくる。親も子もある程度帳尻を合わせられるからです。
親技でもうひと押ししてね、っていうのはこれがあるからで、たとえば一定の成果を出している子供は、取り掛かりに時間がかかるが、取り掛かりさえすれば、ノルマが終わるまでできる子供は多い。
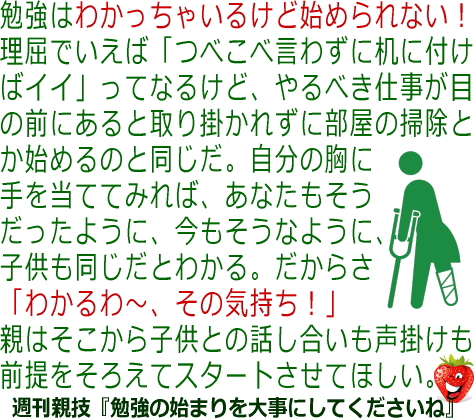
最初の取り掛かりをどうするかだけなんですよね。これが親技で言う「スイッチを入れる」だ。
「勉強の全体を通してみる」から「最初の取り掛かりだけを見る」に移行するのもこの頃だ。あとはチェックをする、確認テストをすることで親の手間が少なくなっていく場合もあるだろう。
移行したら点数や偏差値が下がったということも出てくることがあるし、エラーを出しながら試行錯誤をする時期でもある。受験が迫ってたら試行錯誤なんてできなくなるけれど、受験生になる前だったらそれができる。
生物大好きっ子さんは、その状態を
明らかに「焙煎」の火加減が弱くなっていた、弱くしたのではなく、気づかないうちに火が弱くなっていた。そう、油断していたのは自分だったんです。
幸いにも「火加減」の変化に早く気づくことができたため、少しずつですが元のペースに戻すことができました。
ここに見出して、元のペースに戻ったということは、その分析も当たっていたのでしょう。
このあたりの表現の仕方は
なぜなら「焙煎」の火加減は「自分では弱めているつもりはなくて、いつの間にか弱まっているから。しかも突然「強火」から「弱火」に変わるんじゃなく、「強火よりの中火」「弱火よりの中火」になっているからたちが悪い。
だから時々「焙煎」の火加減が適切かどうかを、親が自ら問う必要がある。
ボクが書いた以上に自分の中で消化されて、もうボクが考える域をはるかに越えて行ってしまった感もありますな。
火を消さない、意識して火加減を弱めることはある、を実践しながら、それが継続してできるなら、しばし待たれよ。2ハゼは起こる。必ず起こる。
ただし、1点、生物大好きっ子さんは、2ハゼまで、しばらく待たねばならないかもしれません。
途中で、1回目の爆ぜ「1ハゼ」が起こると、「子供が全体の上位20%ほどの位置をキープできるように」なれると書きました。
そして、合わせてその「1ハゼ=上位20%入り」は、学年が高くなればなるほど、その確率は低くなっていくとも指摘しました。
「1ハゼ」は誰にでも起きるけれど、
小3よりも小4のほうが
小4よりも小5のほうが
小6よりも中1のほうが・・・・
というように、「1ハゼ」で即「上位20%へ」は学年が上がるにつれて難しくなる。それは内容がそれだけ難しくなり、量が増えるからですよね。
逆に学年が上がれば上がるほど、「1ハゼから2ハゼ」までのスパンは短くなっていきます。
つまり今親技の読者でおそらく一番低い年齢層に該当すると思われる「小3の生物大好きっ子さん」の場合は、それでいうと「1ハゼから2ハゼ」までのスパンがもっとも長い学年であると言えるでしょう。
この「1ハゼから2ハゼ」までのスパンが学年が上がれば上がるほど短くなるのは、主に外部の要因に起因するとボクは考えています。
すなわち「ライバル」「競争心」「他人の目」「先生の評価」「成績表の価値」など外部との関係が学年を経るごとに広がり、外部からの評価の価値が学年が上がるにつれて、子供自身がより強く感じることになることによって、学年が上がると爆ぜるとバンバンと「1ハゼと2ハゼ」が継続してすぐ起こるのではないか。
これはボクの仮説です。
わかりやすくいうと、「小3で偏差値70です」っていう子供はすくないが、「小6で偏差値70です」という子供は多い。
偏差値ってなによ? みんな偏差値が高いってことをどう思ってるのよ?
一般的に学年が上がるにつれて、「偏差値の価値」に気づきはじめる子供は多くなるでしょ?
「あの子は賢い」っていう評価や評判も、子供たちの中では小3よりも小6のほうが一般的には敏感と言えるでしょう。
そうした外部との関係の広がりや外部評価の価値の重みなどが学年が上がるにつれて「頑張る」に直結しやすいからこそ、「1ハゼと2ハゼ」の間隔が狭まって起こるのかもしれません。
「のび太クンよりもボクは成績がイイ。ボクのほうが賢いんだ」っていう感覚って小学校3年生では通常あまり見られない。親がそういう価値観をガンガン吹き込んでいない限り、人の評価に偏差値は大きな影響を及ぼさない。
がゆえに「なにゆえ毎日頑張らないといけないのか?」「なぜ毎日こんなに早く起きて朝勉をボクはしているのだろう?」と無意識のうちに感じやすいともいえるでしょう。
緩む要因は、親の火加減のほかにも子供のおかれている学年や状況もあるとボクは思います。
じゃあ、小3だったら「1ハゼ」が起こっても「2ハゼ」まではしばらく時間がかかるとするなら、ひたすら継続してやれば必ず2ハゼは起こるのか?
継続すれば必ず起こります、2ハゼは。そして自分で勉強もするようになるでしょう。
しかーし、その継続期間は学年が下になればなるほど長くなるから、親のほうがしんどいんですよ。
早く始めてるから期間も長くなるんじゃ、身体が持たないじゃないかって言われればその通り。
ゆえの親技では、本格的な受験勉強期間(具体的には小5からの2年間を正味の受験準備期間とボクは思っていますが)に入るまでは、特にすでに「1ハゼ」も起こり、帳尻合わせもある程度できるのならば、今よりも30分勉強時間を減らせないかと真剣に考えてみるべきだと提案しています。
成績は上位20%の枠を維持しつつ、今よりも勉強時間を少しでも減らせられないかと。
今まで3回繰り返してテストに臨んできたけれど、2回でテストに臨めないか、2回でテストに臨んだらテスト結果はどうだろうかってチャレンジしてみるとか。
生物大好きっ子さんは、その点についてすでにお気づきですよね?
「焙煎」の火加減は「自分では弱めているつもりはなくて、いつの間にか弱まっているから。しかも突然「強火」から「弱火」に変わるんじゃなく、「強火よりの中火」「弱火よりの中火」になっているからたちが悪い。
だから時々「焙煎」の火加減が適切かどうかを、親が自ら問う必要がある。
火加減を今までよりも強火にして同じ時間煎ると、豆(子供)の焙煎の度数は上がってしまう。それは上位20%よりももっと上へ行こうとするのとやっていることは同じになります。
もちろん今よりももっと上に行くことは否定はしません。そうしてもイイ。
ただ長い戦いです。終わりなき戦いです。
「2ハゼ」も起こして、早い段階で自分で勉強できるようにもさせたいっていう野望があるとするなら、今までよりも少ない勉強時間で今の成績を維持できないか、そうするためには何が必要かってことは本格的受験準備期間に入る前に親子でチャレンジしてみる価値はあるとボクが思います。
親技で言う「小5の壁」は難易度が上がり、やる量が1週間で今までの2倍になった時、越えられない人が出てくる。
3回繰り返しやらないで1回で、1回目から「速く解ける」ようになるためにはどうしたらいいか。授業でのお土産、理解力の向上、集中力、計算の工夫、正解で満足せずにラクな別解を考えてみる…etc
いろいろと考えるべき点はありますが、出発点は「今までよりも少ない勉強時間で今の成績を維持できないか」、そして「そうするためには私たちにとっては何が必要か?」、加えて「すぐできることは何か?」です。
「これから1か月間、今までよりも1日の勉強時間を30分減らして今の成績は維持できないか、チャレンジしてみないか?」から始めたらイイですね。
今の状況、今の学年を考えれば、仮に成績が少し落ちたとしても、元に戻す経験はもう知ってる。
その経験をした上で、再び同じ勉強時間に戻したとしても、30分減らしてみた経験を知っている子供と知らない子供では、今までと同じ勉強時間でも意味が違ってくるのではないでしょうかね。
今まで3回繰り返しやってテストに臨んでいた子供が「もう3回はできません」って言ってきたら「じゃあ、2回で処理しろよ」って言う。
「いいんですか? 2回で終わって・・・」
「いいよ、だってできないんだろ? 3回はできないから2回でやらなきゃいけないって気持ちでやれよ。どうせ3回やるんだからって甘くなっていたところもあったんじゃないか。厳しくいけ。2回で勝負しろ。どうしても気になるものだけ3回やればイイじゃないか」って言う。
そしたら3回のところを2回で行っても、たいていは成績は下がらない。ホントですよ。下がった奴はあまり知らないなあ。
3回繰り返しやる意味を知っている子供は、意味を知ってそれを2回にするなら成績は下がらない。
親は2回にしても下がらないためには、なにがいるのか?って観点をフォローしてやればイイ。
静寂から「2ハゼ」へ。そのためにはもっと今の勉強がラクになるためにはどうするか。ラクになったのに成績が維持できるってするためにはどうすべきかを試すこと。
ハイタッチしながらね、エラーも出しながらね、いろいろ知って受験準備期間へ。そしたら「小5の壁」なんて「壁なんてあったかなあ?」ってなるからさ。頑張ってください。
長くなりましたね。ここまで読み続けた人はあまりいないと思うわ・・・反省。おしまい!
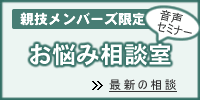
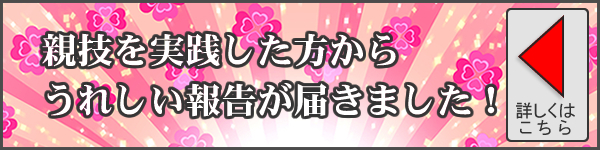
中2 笑ママさん
9月19日実施公開テスト
偏差値上がりました!!
英語50.9→63.8
数学51.8→52.3
国語59.3→58.8(下がっている!)
理科55.0→69.2
社会60.3→64.2
3科54.2→59.5
5科56.3→63.87月末に中1からの結果報告をさせていただき、「イケドン法を見直してみてください。」との返信をいただきました。
「見抜かれている!」とギクッとしました。やり方が徹底していなかったのです。
そこで、「夏休みは教科を超えて苦手単元を克服するぞ!」と英数は(中2・1学期の復習内容)のため塾の夏期講習に参加、あとは家で理科(中1・ちんぷんかんぷんの単元)&数学(苦手単元)をつぶす!を目標に鉄則8&9でトライしました。
でも、中2から部活に入ったわが子にこの夏の暑さは厳しく、熱中症のような状態でバテバテ、短期集中とはいきませんでした。
塾の内容(英数)はイケドン法をこなし、理科も3単元のみしっかりおさえましたが、数学の1年の苦手単元克服には全く手がつけられませんでした。
9月からは、英数のみ塾を続け公開テストに向けてはまだ習ってない範囲を(理社2単元ずつ)問題集で勉強しました。
とりあえずやれることはやったが、結果はどうなるか?と思っていたら、こんなに上がってびっくりしています。子供もすごく喜んでいました。
数学は今回勉強した単元での正答率はA問題90%・B問題79%だったので、これから弱い単元をしっかり押さえていこうと思っています。
数学に力を入れてこれから頑張っていきましょう!
すでに申し上げたようにやる問題を多くするのではなく、1問1問を丁寧にやるようにしましょう。
習ったら、入試問題レベルまで落とし込む!ファイト!