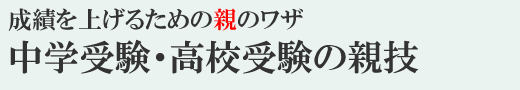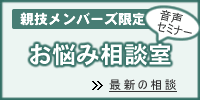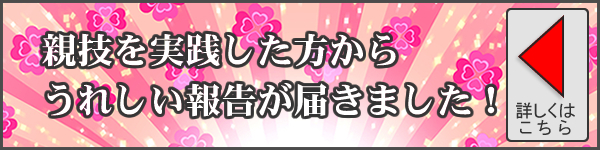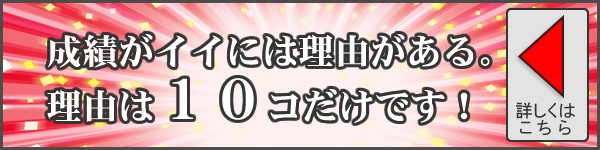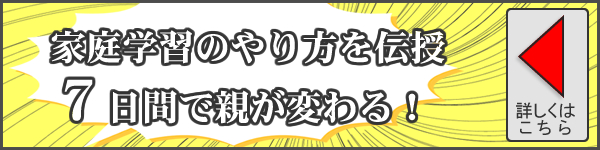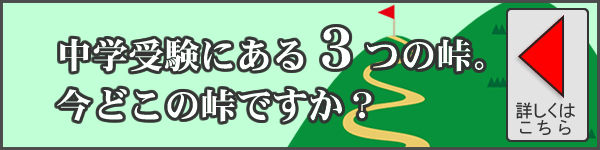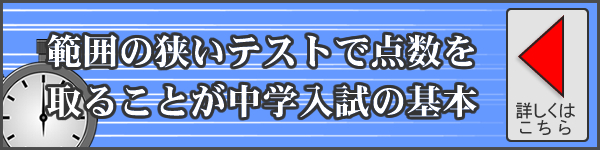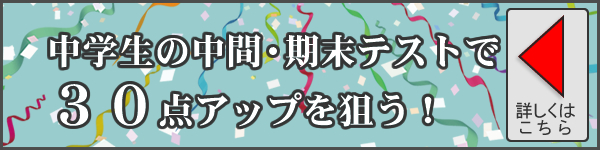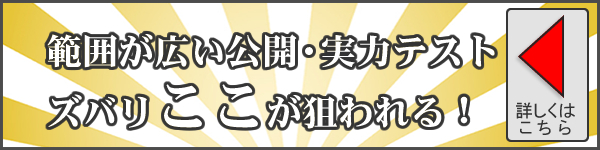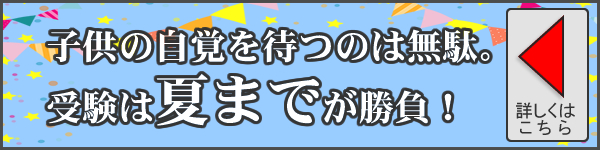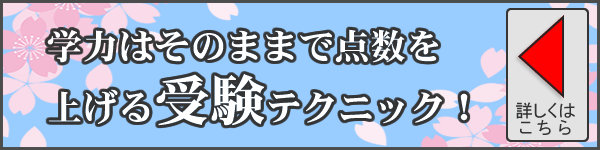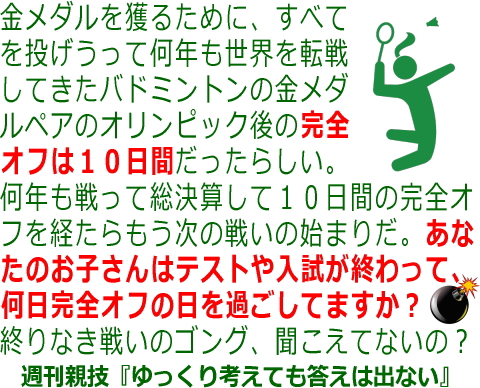
こんにちは、ストロング宮迫です。
オリンピックを題材に親が子供の勉強を見る際の学ぶべき点については、過去10数年の間に多数取り扱ったので、もうだいたいよかろう….と思っています。
ただ、これまで取り扱ってこなかった点があったので今回はそれを取りあげてみようと思います。
もうテレビなんかのニュースで見たと思いますが、オリンピックが終わってたったの1ヶ月ですが、すでに選手たちは始動を開始して、試合も始まっています。リオオリンピックのバドミントンの金メダルペアは先日ジャパンオープンで決勝まで進み、決勝戦はリオと同じ顔合わせだったとか。
金メダルは獲るのもタイヘンだけど、獲ったら獲った後がさらにタイヘン。祝勝会に、関係者への挨拶回りに、イベントに凱旋パレード…etc
それなのに、もう1ヶ月もしたら、次の戦いが幕開け・・・「もういいです」って言いたくなりますよね。
彼ら彼女らは受験生が入試を終えた後の100倍くらい忙しいわけです。オリンピックや今回の入試で「引退」するなら、それでいいけれど、そうはイカの●ンタマの場合がほとんどだ。
金メダルを獲るためにすべてを投げうって何年も世界を転戦してきたバドミントンの金メダルペアの完全オフは10日間だったとか。
・・・五輪から帰国後の10日間は完全オフ。高橋は「昼くらいまで寝ていたこともありました」と笑う。体重は約1・5キロ減少。
今月5日の練習再開当初は「思っていたより体が動かなかった」という。高橋は「これだけ練習していなくても決勝にいけるんだと、ビックリ」と目を丸くした。
どうです? 10日間の完全オフって長い? 短い?
普通に考えれば「すくなっ!」って思うんじゃないでしょうかね。
しかーし、受験生でたいしたことのないテストが終わった後で10日間の完全オフっていう子供は割と多いんじゃないのか?
入試が終わって入学式までの1ヶ月とか2ヶ月とかを完全オフにする受験生も未だ後を絶たない・・・
だから、親技を創めた当初からボクらは言ってる「受験が終わり10日で次の勝敗が決まる!」ってさ。
終わりなき戦いなんですよ、子供たちの闘いはね。もちろんオフもあってもイイんです。
でも、ちょっとしたテストがあったからって「勉強をゼロ」にする必要はないよ。オフにするほどオンでやってないんだからさ。
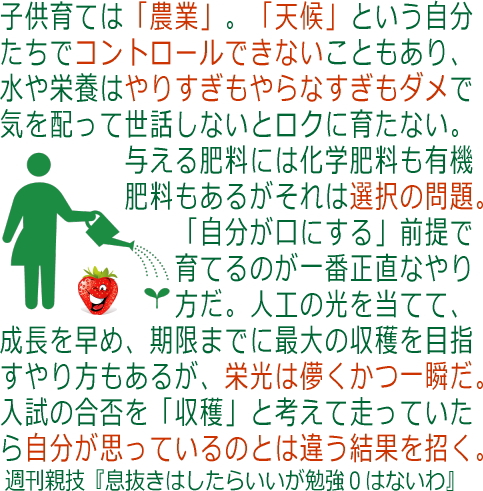
オリンピック同様、長い年月をかけて戦ってきた受験だとしても、入試が終わって1ヶ月も2か月もオフにする必要はないし、仮にそれだけの期間をオフにしたら、次に始動するまでに倍の時間がかかる。
もっといえば、入試以来、もう二度と始動できない人になってしまう可能性も大いに秘めているから、ボクは口うるさく言っているだけなんです。
ダイエットも散歩も、そして勉強も当たり前の習慣とするために時間がかかる。多くは習慣になる前に挫折するか、中途半端なことをやって終わりになるのが大半だ。

歯を磨くみたいに、勉強できるようになるためには、長い時間とフォローする人(コーチ)と成果が必要不可欠です。なにか1つ欠けても、習慣化「歯磨き状態」まではいかない。
フォローする人(コーチ)は一番身近にいる親が一番手っ取り早く、親がコーチするなら最初は短い時間でイイからまずは「成果を出す」考え方やその術や意識がコーチ側の親にどうしても必要だから、親技がある。
3日やって3日分の成果を出すのはみんなできる!それがスタートで、そのスタート地点にはみんな立てる。まだそのスタート地点に未だ立っていない人もいるけどね。
ただ、そこから多くの親が望む「自分で勉強する」「自分で考えて勉強する」「自分で計画立てて勉強する」「自分に必要なものを区分けして勉強に励む」の段階に進むには一定の時間、長い時間がかかる。
3日やって成果出して、「どうして習慣化しないのかしら? どうして自分で考えて勉強しないのかしら?」って嘆かれても、ボクも困る。
3日間の断食なら誰でもできる。でも、4日目からめしを食えば、3日もすれば体重は元に戻る。ダイエットはずっと継続するから身体にとっても良い影響があるんであって、3日断食して3日食いまくって、また3日断食して・・・なんていう無理なことを繰り返せば、身体が壊れる。
この理屈はみんな理解できる。それは子供の勉強も一緒だ。
しかーし、子供の勉強の話になると、途端に「なぜウチの子は自分で勉強しないのか?」なんて話にすぐいっちゃう。とってもおかしいとボクは思うけど・・・
じゃあ、どれくらいの時間がかかるのかって話になると、いつもここで書く「1万時間」の話になるけれど、「1万時間は相当なレベル」ですから。
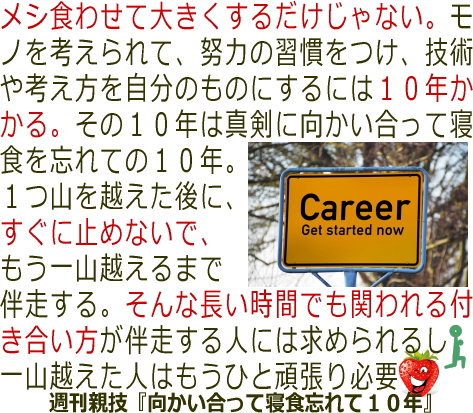
じゃあ、「自分は5,000時間でいきます!」だってかまわないし、3,000時間の親がいてもかまわない。でも、習慣化してできるようになるには一定の時間はかかるってこと。
子供たちは、長い旅路を歩くから、正確に言えば「長い旅路をこれからもずっと歩いて行かねばならない」から、無理せずに、ずーーーと歩き続けられる速度で歩いたらどうですかっていうのがボクの提案です。
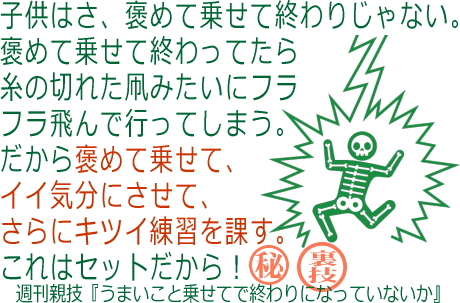
でも、多くの親は手を打つのが遅くて、受験が迫ってから勉強について取り組みだすから、スタート地点でスケジュールを考えてみたら、短期間で大幅なすごい成果を出さねばならないという、走り始める前から無理な計画となり、「子供の今」や現状把握や現状分析をしない無理な計画ゆえに、その旅路は地獄となる。
旅路が地獄でも一定期間を過ぎれば天国を約束されているなら我慢できるけれど、過程が地獄なら結末も地獄に決まってる。
灰色の受験生活のあとはバラ色にはならないから。
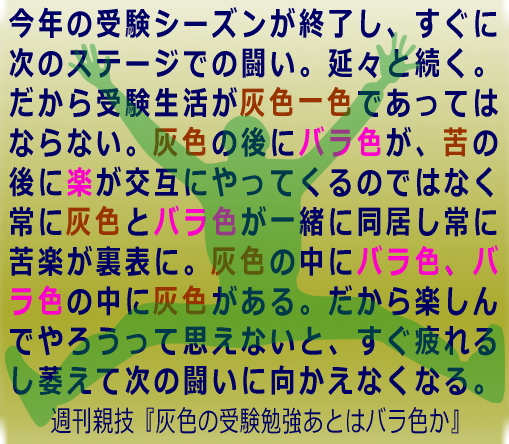
バラ色を、入試が終わって勉強もせず、好きなことを無制限に何でもし放題という意味での「バラ色」や「天国」とするなら、それは確実に来るけれど、その後の学校生活や次の入試そのものは文字通り地獄になる。
だから、覚えておいてもらいたいんです。
金メダルを獲った人の完全オフは10日間だった!と。
あなたのお子さんが金メダルを獲った人に等しい努力をしたなら、あなたのお子さんにも10日間の完全オフをあげたらよろしい。
でも、10日間も完全オフにしていい子供は、事実上ほとんどいないとボクは考えています。実際、今回メダルを獲った選手たちの中には、先のバドミントンの選手同様、世界へ転戦を「もう始めている」選手もいる。
10月7日に東京都内でリオデジャネイロ五輪・パラリンピックのメダリストたちの合同パレードが開催されるそうですが、日程の都合で参加できない選手がたくさんいるそうです。
朝日新聞が各競技団体などに問い合わせた結果では、競泳陣では女子200メートル平泳ぎ金メダルの金藤理絵、男子400メートル個人メドレー銅の瀬戸大也が不参加だ。ともに北京、ドバイ、ドーハとワールドカップ(W杯)を転戦するためで、今月28日に出国する。
卓球男子団体で史上初の銀メダルの原動力になったエース水谷隼も、所属するロシアリーグ・オレンブルクの試合のため、国内にいない。
もうね、1ヶ月も過ぎちゃうと、次の闘いのゴングはなってるんですよね。
それはオリンピック選手に限らず、子供たちも一緒。そして、その意識はコーチである親にまずないと、コーチが2か月の完全オフになっちゃってると、どうしようもないから。
じゃあ、私たちは休めないじゃないかって!?
そうなんですよ・・・休めないの。ずっとずっと、いつまでも続くんです、この旅路は。死ぬまでね。
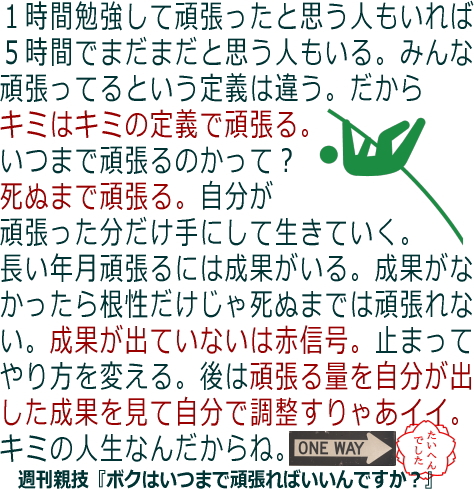
それをしんどいとか辛いと思うのは個人の自由だけど、だからこそ、無理なく長く継続できる行動や実践を考えてみる価値がある。
完全オフが1か月なければ、やりたくありません!という訓練や勉強は、そこに無理があるってことです。やろうとしている勉強に、現状では無理がある。
入試というスケジュールが決まっている枠組みのものを考えたら、今はこうでなければならないという目安はあるけれど、そこまで今達していないからといって、無理に突っ込むと、1か月の完全オフを子供が求めたくなるから。
親も大変で無理なことを子供に課したら、やるのは子供でも、親も気持ちが辛くなって、つい「受験まで頑張ればあとは・・・」ってなっちゃうから。
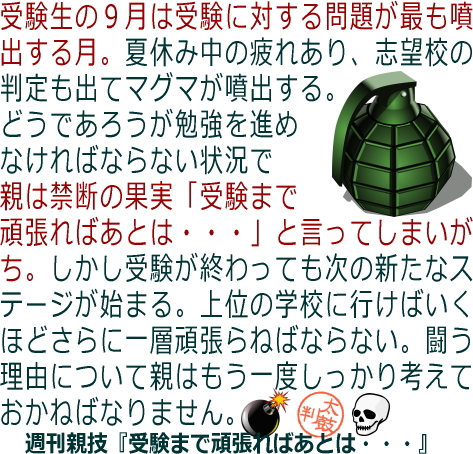
なにがその基準になるかは、各家庭でみんな違う。
「1万時間」付き合うのか、「5,000時間でいきます!」なのか「3,000時間で許してください」なのかは自由だし、親ができる範囲で設定すればイイ。
これらについては、これまでにも何回も触れてきましたよね。今回ぜひ触れておきたかったのは・・・さっきの記事、短いのでもう1回だけ読んでみてもらえませんか。これです。
・・・五輪から帰国後の10日間は完全オフ。高橋は「昼くらいまで寝ていたこともありました」と笑う。体重は約1・5キロ減少。
今月5日の練習再開当初は「思っていたより体が動かなかった」という。高橋は「これだけ練習していなくても決勝にいけるんだと、ビックリ」と目を丸くした。
この記事のうちの、後半部分なんですよ、ぜひ今回読んでほしかったのは。
「これだけ練習していなくても決勝にいけるんだと、ビックリ」
↑↑これね。
死ぬまでずっと続く旅路なんだけど、そう考えるとものすごく苦しい道のように思えるけれど、あなたの周りにいるずっと頑張っている「成績がイイ子」はそれほど苦悩を浮かべていないということに気づくはずです。
タイヘンで厳しくて苦しいはずなのに、どうしてあんなに朗らかなんだろうってさ。
いかなるレベルの子供にだって悩みも苦悩も苦労もあります。でも、ここまで書いてきたように、どうにもならない苦しい道って感じを成績がイイ子からは受けない。感じられない。
それは、訓練を重ね、蓄積をし、成果を出して、習慣化していくと、
「これだけ練習していなくても決勝にいけるんだと、ビックリ」
こういう現象が出てくるからだ。
勉強時間は前と同じなのに成績は上がったとか成績が維持できたという話は聞いたことがあるでしょう。
もっといえば、その過程では、勉強時間が減ったのに成績は上がった!という現象さえ起こり得る。これまで何度も目にしてきました。
それが「こんなに勉強していないのにこの順位や偏差値が獲れるんだ」っていう事象です。これが頑張り続けてきた子供へのご褒美なんです。
そこに行くまでに長い時間もかかるし、無駄な勉強もしてきたし、フォローしてくれる人の叱咤激励もあって、まわり道をしながらも継続して歩いてきた。その苦労や時間がそのままこれから先も続くのかっていえば、そうじゃない。
だから、苦しい、辛い、死ぬまでやらないといけないんだって暗い顔をしなくてもイイ。頑張ったらさ、ご褒美があるから。
歯磨きを正しくきちんとすれば、虫歯にならない。あのイヤなキーンって音の歯医者に行かなくてもイイ。歯磨きをしたご褒美の1つはこれでしょう。歯医者に行かなくてもイイなんて、みんなたいしたことがないように思うかもしれないけれど、ボクはすごいご褒美に思えるけどね。あなたはどう?
勉強でもそのご褒美がくるんです。信じられないなら成績がイイ子に聞いてみればイイ。もう大きくなっている人がイイですね。負荷はさ、無限大に膨らんでいくわけじゃないってことなんです。
賢さや狡さが身に付いたり、先読みや推測や見立てができるようになると(それは今までの蓄積が貯金となるってことです)、今までよりも短い時間で解決までたどり着くことができるようになる。
言葉でいえば、たとえばそういうことが起こることになって、負荷が無限大には膨らんでいかないってことなんです。
負荷がなくなることはないし、かかる負荷も質が向上してキツさも変わらないんだけど、同じことをしても取り分が多くなる。
親になって、大人になってさ、子供の算数の問題を見たら、子供がどうして「これくらいの問題を難しく思えるのかわからない」って感じる瞬間があると思います。あんなに子供の頃に難しく思えた「あの問題」だって、今なら忘れてしまっていて解けないまでも考えることはできる。それが子供にも起こるってことです。
再び登場してもらいましょう、あのコーチに。
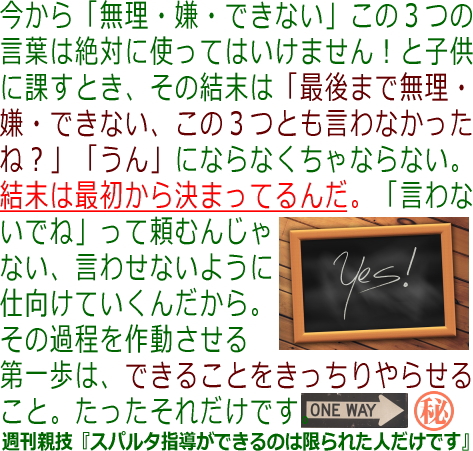
第10回アジア水泳選手権大会(11月17~20日)のシンクロナイズドスイミング選考会が22日、都内で行われた。
代表チームは2020年東京五輪・パラリンピックへ向けて動きだしており井村雅代ヘッドコーチも、選考会での選手の泳ぎに鋭い目を光らせていた。「東京で戦うには選手の大型化を目指したい。今日の選考を踏まえて10月10日にアジア選手権のメンバーを決めたい」と、今後の予定にを説明した。
ひときわ言葉が鋭くなったのは、デュエットで乾と組みリオ五輪で銅メダルを獲得した三井梨紗子の名前が出た瞬間だった。
引退とも現役続行とも明確な態度を示さず、21日のミキハウスの主催の報告会では「引退というよりもゆっくり考えたいです」と立場を説明していたが、井村HCは容赦なかった。
「休養という立場ですが」との質問が飛ぶと「何をふざけてんねん。あり得ないそんなこと」と一刀両断。
「彼女は私に引退を伝えました。正式な書類も出ています。それが事実です。私は『もっと力を使い切って終わりにしたらどう?』と(現役続行を)勧めましたが『もう泳ぎたくない』とはっきり言いました。休養して戻れるほど甘くはない。もう戻る場所はない」。
HCの立場から明確に「もう泳ぎたくない」と明確な意思を示した三井は戦力外との態度を示した。
語気が強まり、早口に無念さをほとぼらせた井村HCは、時折無念な胸中ものぞかせた。
「彼女はまだ限界じゃない。それは伝えたし、力はまだ伸びると思う。水着のサイズも2サイズも変わって、本当に力がついたのに。リオ五輪で銅メダルを取って、彼女はようやく一流に入ったところなのに」と、厳しい中にも三井への愛情を感じさせる表情も見せた。
しかし、11月のアジア選手権に来年は世界選手権も控えている。三井が抜けたデュエットの構想も、代表チームの編成には待ったなしの状態だ。「私は北京五輪でホスト国のHCを務め、開催国で五輪に出ることのすばらしさを体感した。あんな、素晴らしい思いを感じないでやめてしまうなんて考えられない。三井は臨めばその体験ができるというのに。何もリオ五輪までの2年と同じような厳しい時間がこれから4年続くわけじゃない。メダルを獲得して新しいシンクロとの付き合い方がはじまるのに…」と、未練を口にしつつ先を見詰めた。
この記事の中のここね↓↓↓
何もリオ五輪までの2年と同じような厳しい時間がこれから4年続くわけじゃない。メダルを獲得して新しいシンクロとの付き合い方がはじまるのに…
シンクロは井村コーチのもと、まさに文字通り地獄の練習を重ねて今回メダルを取り戻した。合宿が100日とか練習が12時間とか、その厳しさは皆さんもオリンピックの報道で聞いたことがあるはずです。
シンクロ王国でメダルの常連だった日本は井村コーチが去った後から地盤沈下して前回のオリンピックでは屈辱のメダルなしとかだったんでしょ?
井村コーチが復帰してきて、井村さんは選手の身体を見て「この子ら、練習してへんわ」って思ったとか。技術の前に身体つくりから、つまり1から始めないといけなかった。ゆえに訓練は地獄を究めた。
でも、もし選手の身体はメダルを獲るのに十分だったとしたら、そこまで地獄の訓練は必要なかった。身体を作るのは1からやらなきゃいけない。0からの構築です。時間がかかる。しかし、オリンピックの日程は決まってる。そこまでに仕上げなければならない。
どうするか?
決まってます、地獄の訓練さ。それをやり切ったから今回のメダル。
実際にやるわけじゃない、話を聞くだけでイヤになりそうな訓練を彼女らはやり切って今回の結果を得た。あまりにも厳しい練習すぎて、二人ほど代表選手を辞退したと報じられたのはオリンピックの前でした。
だからね、ボクら凡人は終わったあと「もう二度としたくない」って思うような勉強は最初から子供に課さないほうがいいんじゃないって提案したんです。ガっとやってサッと離れてしまうなら、ずっと継続できるような勉強をしたほうがイイんじゃないってさ。
この記事の「引退というよりもゆっくり考えたいです」っていうのは、過酷な受験を終えた子供たちからこれまで何度も聞いてきたもの。
返す言葉は井村コーチもボクも一緒だ。↓↓これね
「彼女はまだ限界じゃない。それは伝えたし、力はまだ伸びると思う。水着のサイズも2サイズも変わって、本当に力がついたのに。リオ五輪で銅メダルを取って、彼女はようやく一流に入ったところなのに」
入試を終えた子供たちが入学式の前にすごく伸びるっていう現象もこれに該当する。入試1か月前から子供はもう一伸びするけれど、入試後から入学式までは二伸びするからね。ほとんどの子供は入試で止まるから知られていないけど、ホントですよ。
でもね、「あの練習」や「あの勉強」を思い出したら、気分が悪くなるんですよ。「もうええわ」ってさ。それくらい頑張り切ったわけだしね。
ただね、選手がコーチの気持ちを100%理解できないように、子供も親や先生の言うことを100%受け入れられないのも事実なんですよ。
「もうええわ」ってなったらね、やりきった!って思えたらね、歩みは止めたくなるものなんです。シンクロはね、やめても、また次の道があるじゃない。
でも、勉強はね、入試を終えても、また勉強が始まるからさ。終わらないのよ。
だとしても、やっぱりボクも井村コーチと同じことを言う。
何もリオ五輪までの2年と同じような厳しい時間がこれから4年続くわけじゃない。メダルを獲得して新しいシンクロとの付き合い方がはじまるのに…
厳しい道には違いないけれど、これから見える風景は今までは別の風景なんだよって。だから歩みを止めないで行けって。もう身体つくりはできたんだし、さらなる成長をするにしても、基礎体力のレベルは2年前よりも断然あるわけだから、同じ練習だとしても室が違うし、もう一段か二段上の景色が拝めるってね。
でも、子供は言うんだな、「引退というよりもゆっくり考えたいです」
ただ考えてもね、答えは出ないんですよ、実際は。
歩みを止めたらね、最初だけだけど、無性に戻りたくなる時が出てくる。そこがね、最後のチャンス。アドレナリンが出まくってた時の感覚が残っているウチがチャンスです。帰っておいで。
井村コーチの「リオ五輪までの2年と同じような厳しい時間がこれから4年続くわけじゃない」、この言葉にウソはない。ホントのことだから。
今までよりもラクになるとはいわないが、今までのような苦しさではないという感じです。
時間が経つとね、戻りたくなっても戻れなくなるんですよ。もう戦えなくなうんだな、哀しいけれど。そんな中高一貫生や高校生も、これまたたくさん見てきたからさ。
迷っているときに、誰かが強制的に戻しちゃえばイイんだけど、合格とかメダルとか勲章を一つ手に入れると、それもなかなか難しい。戻すことは難しくないんだけど、そこからもう一段上がった景色を見るためのモチベーションが難しんです。
同じ努力でも質の転換が求められる世界に足を踏み入れることになるからね。自分の「普通のレベル」も上がっちゃってるから、考えて練習しないと、すぐやってられないって思うから。
でも、「そうするだけの価値がある」と思います。いかなる戦いであっても、戦いながらボクらは学ぶんだから。
あなたのお子さんが死ぬまでうんうん継続して押せるようになるための負荷を、今かけていますか?
負荷はかけすぎてもダメで、かけなすぎてもダメなんです。負荷の量が適当かどうかは、誰かが答えを持っているわけじゃない。子供の反応が正解です。
子供を観察して増やしたり減らしたりする。さあ、あなたは子供に「何時間・何年」かけて面倒を見るつもりですか?
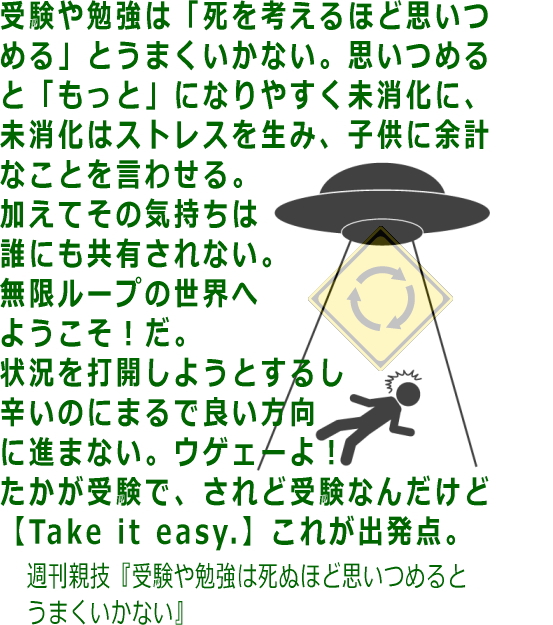
『10の鉄則』の感想、続々と・・・
中2ぴょこちゃん
引き込まれるように最後まで読みました。
わかってはいても実行できなかったことが、わかってきました。
育児に関する本は何冊も読んだことがありますが、成績を上げるための本はたぶんはじめて読みました。
10の鉄則を読んで、あらためて息子はこの家が育ててきた子供であると思いました。
息子の好きなことに関しては、10の鉄則がほぼ守られていますが、嫌いなことに関しては1から10まで鉄則が守られていません。おそろしいことです。
現在は、もちろん困っている状態なので、手をつけていなかった部分つまり子育てにおいてスルーしてきたことを実践しなくては、という思いでいっぱいです。
反抗期前は、そこそこすべての勉強ができていたので安心していましたが、反抗期がはじまり、好き嫌いが激しく、なかなか大人の言うことに納得しなくなくなってから、成績がガタガタになってきました。
もともと好きなことからやらせてきて、嫌いなことを納得させてやらせてこなかったので、親子で苦しみながら乗り越えて行きたいと思います。
ただ、経験に基づくノウハウに乏しいので、そちらのヒント、アドバイスを頼りにしています。よろしくお願いいたします。
我が子を見て、やっぱり自分が育ててきた子供だなあと高校生や中学生になるとよくわかりますよね。
もう少しうまくやってきたつもりだったんだけど・・と思いながらも、高校生になれば、驚くほど似てくるんだなあ、これが。
だから子供を見るのは自分の鏡と思うのがいいんでしょうね。
自分は自分を見ることができないけれど、子供を見れば、自分を、もしくは自分がしてきたことを見ることができる。
だから、ボクは、我が子にボクよりも少し上、自分が越えられなかった壁を1つだけでも越えてくれたらいいなあと思っています。