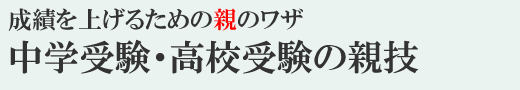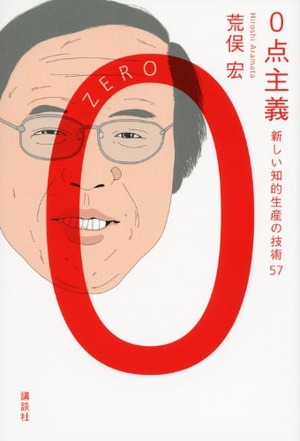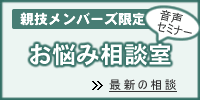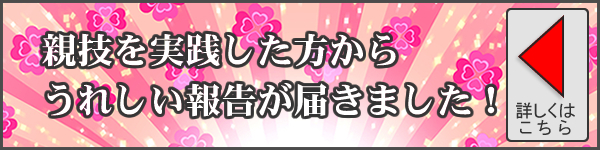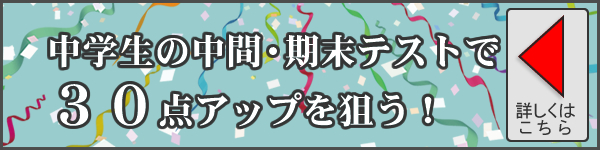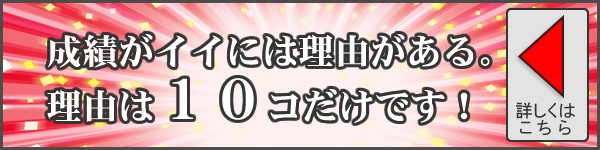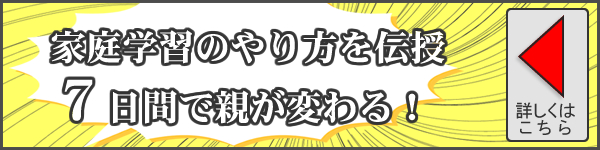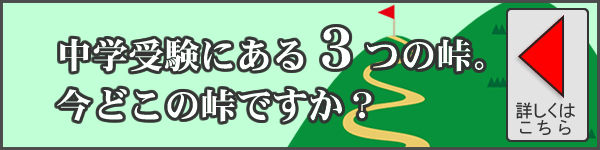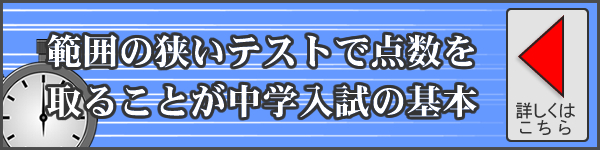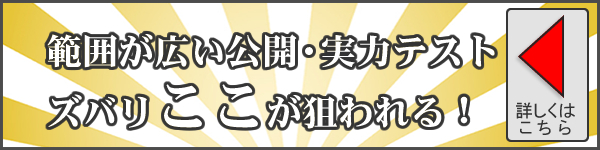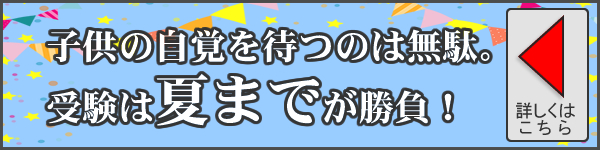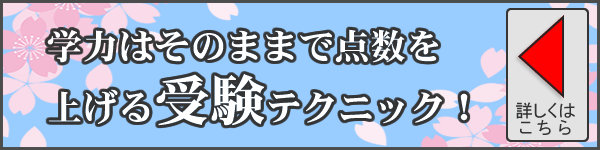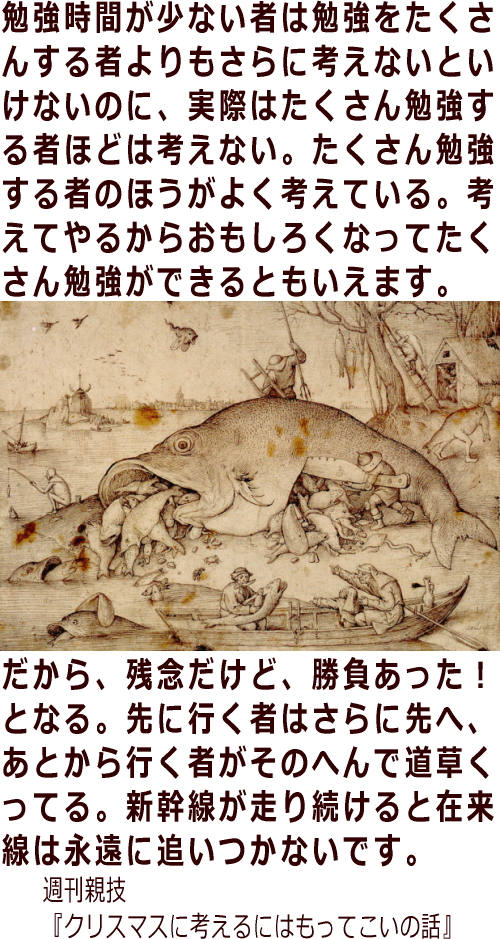
こんにちは、ストロング宮迫です。
ニューヨークタイムスの写真を見ると、アメリカはすごいことになってますが、
ホリデーシーズンの全米宅配便事情。とりあえずこの写真見てやはりアメリカへの荷物の梱包はがっちりしなくてはという気にさせられた。 http://t.co/jDnb04V5oo pic.twitter.com/T2kS8m80OY
— suisei_sensei (@shoemaker_levy) 2014, 12月 23
日本も似たようなもんですかね。
受験生はそれどころじゃないのはもちろんですが、まあ世間の流れなんてうつろいやすいものですから、うっかり浮かれたり、流されないように気をつけたいものです。
本日も昨日に引き続きステキな講座が開かれております。
理学。それは自然の真理を追究する基礎科学です。 東京大学理学部では世界をリードする Top Scientists による高校生のための特別授業を公開します。
講義1「恐竜の研究~フィールドワークから現生生物との比較まで~」
地球惑星環境学科 對比地 孝亘 講師講義2「植物が花を咲かせるしくみ~花成ホルモン・フロリゲン~」
生物学科 阿部 光知 准教授
※この毎日親技は2014年12月25日に配信したものです
なにせ日程がすばらしいですわ、12月24日、25日の2日間ですから(^^)
個人的には「植物が花を咲かせるしくみ」なんていうのはなかなか興味深いテーマですが、中年のオヤジのストロングが聞いてもねえ。
ただ子供たちには興味があればこういうのに触れてほしいですね。やっぱり子供たちは今この瞬間何を見るか、なにに触れるかが将来の道に微妙に大きく影響しますから。
勉強のことだけじゃないですよ。ゴルフの松山選手も6歳の頃のことをまざまざと覚えているとか。
6歳の時、故郷愛媛県のゴルフ場で青木功と対面したエピソードは既に多くの人が知るところ。
「青木さんはもちろんだけど、色々ありますよ。中嶋常幸さんにも7歳の頃に会ったことがある。2000年、大阪でダンロップのプロアマ大会に父が出ていて、付いて行ったら、中嶋さんがいた。今でも覚えている。練習場の一番左端の打席だった。
50ydくらいのロブショットを3連発して、3球とも同じところに落ちて、”ひいた”。
霧がすごくて軌道は分からなかったけれど、同じ打ち方で、同じように霧の中にボールが消えて、まったく同じところに落ちた。『すっげえ…』って、ひいた(笑)」
「だから子供は大事にしたいなって思う。子供の記憶って、すごく残るんですよ」
日本のゴルフ界を牽引したレジェンドたちに憧れ、夢を見た少年時代。その時と同じように・・・
ああ、だからといってなんの前フリもなく、親の趣味嗜好で東京大学理学部の特別授業に連れて行ってもダメですよ。東大理学部の特別授業は高校生向けですが、興味がない高校生が行ったらかえってイヤになったりしますからね。
子供と触れたものの距離感があり過ぎると、逆に遠ざけてしまうことになりますから。聞いて「おもしれぇなあ~」と思える下地はいる。
なんでも連れていって見せて触れさせりゃあいいってもんじゃない。意識が高い親もそこを間違えている人は多いです。
いろいろ連れて行っているのに・・・・と思っている人はそこがズレてる。
エベレストの頂上にすげぇー「エサ」がありますとかいって、誰が食いつくもんですか。目で「エサ」が捉えられていて、ひとっ跳びしたところに「エサ」はないとね。
とにかくわかったり、おもしろく思えたり、すげぇーって思える範囲でないと、子供は自分のほうに引き寄せられないからね。でも、それがあるなら6歳でも感じられるってことです。
成功者が共通して持つ「グリット」という能力
ペンシルバニア大学アンジェラ・リー・ダックワース氏数年の教員生活を通して、私は1つの結論を見い出しました。
教育に必要なことは、心理学的な見地から、もっと子供たちを理解してあげること、もっと子供たちがモチベーションを高めながら学べる環境をつくってあげることだ、と。
・
・
ですが、私が自信を持って言えることは、生まれ持った才能や知能はグリットに関係しない、ということです。生まれつき素晴らしい才能や知能を持っているにも関わらず、十分な結果が得られなかった人はたくさんいます。それはただ単に、その才能・知能を伸ばすための長期的な、継続的な努力が足りなかっただけなのです。これは私たちの研究結果において、とても明確に証明されています。
前にもここで書きました。
毎日30分の勉強を真剣にするとして1週間で合計3.5時間です。
6日間勉強しない子供が追いつくために日曜日にまとめてやるとすれば3.5時間勉強すれば追いつける計算になります。
計算上はそうなんだけど、1日30分勉強できない子供が1日3.5時間真剣に実のある勉強するのは困難です。
1週目はそれでもできるかもしれないけれど、2週目は・・・4週目まではもたないというのがストロングの考えです。
宿題以外に毎日のルーティンワークが確実に課せられる高校生や中高一貫生なんかはそれがリアルに出ます。それが一番よく出るのは英単語や古語など覚えて小テストがされるもの。
1日やらない子供はあっという間に追いつけなくなるんです。1回飛ばしてあの「蜜の味」を覚えるともうダメだ。
毎日地道に、でも確実にやるべきことを淡々とやる。これがいわゆる「高校の壁」といわれるものです。「高校の壁」は習慣の壁と言い換えてもいいし、地道な努力の壁といってもいい。
毎日1時間真剣にルーティンワークをする子供は年間で365時間。365時間を24時間で割ると「たった丸15日」ほどです。
でも、その1年間で「たった丸15日」が永遠の差になる。2年、3年、4年・・・
いったんこうして毎日確実にルーティンワークを始めた者には、事実上追いつけなくなるのが本当のところです。ゆえに奇跡を夢見るな!ってことです。
もし、この確実にルーティンワークを続ける者がそのルーティンワークの意味ややり方を工夫し始め「付加価値」をつけ始めたら、もうかなわない。
INAC神戸に何が起きていたのか webスポルティーバ 11月23日
澤穂希は「ウォーミングアップは体を温めるだけのものではない」という。
たとえば二人一組でロングボールを蹴る数分間は、長くボールを運ぶためだけのものではない。ボールの当て所、蹴るボールの種類、正確さ、受けるときのファーストタッチ、その際の自分自身の筋肉の感覚など……
気にすべきことを挙げればキリがない。すべてのメニューに付加価値をつけるのは自分自身だ。
体幹トレーニング、走り込みも同じ。出場機会が限られる選手も多いが、だからこそ、ベースの部分はしっかりと高めていなければならなかったはずだ。
・
・
・
わずかな出場機会にかける選手たちはさらに気持ちを強く自分に厳しくしなければベースは高められない。こじゃれたパスを1本通すよりも、まずは的確なパスを3本通すことが先決だ。
あとからやってくる「出場機会が少ない者」は、先を走る者ほど考えていないことがほとんどです。
ただボールを蹴っている。何も考えずにボールを蹴る。しかし、先を走る澤穂希選手は確実に休まずにルーティンワークをこなしながら、ウォーミングアップでさえ付加価値をつけてやってる。永久に追いつけないですな。
勉強時間が少ない者は勉強をたくさんする者よりもさらに考えないといけないのに、実際はたくさん勉強する者ほどは考えない。たくさん勉強する者のほうがよく考えている。考えてやるからおもしろくなってたくさん勉強ができるともいえます。
だから、残念だけど、勝負あった!となります。ここに世の中というと大きくなるから、入試の現実があるといいましょうか。
先に行く者はさらに先へ、あとから行く者がそのへんで道草くってる。走っている線路が違う。新幹線が走り続けると在来線は永遠に追いつかないですよね。
もっといえば走り続ける者は走り続けられるスピードがいかほどかも知らなきゃいけない。100メートル全力で走っても、その後歩いてたり、道草食ってたら、すぐ追いつかれるからね。
中学入試、高校入試までしか走るつもりがない者は、「途中下車」と表現することができる。入試の後も同じか、もしくはもう少しギアを上げて走らなければなりません。だって入試で入った場所はひとくくりの同じレベルの選ばれた者がきてるんだからね。
難しいですよね。難しいと思っている人にステキな言葉を贈ります。
其言簡
其理直
其道峻
其行孤
えっ、いつまで走るのって!?
ずっとよ!ずっと!
だからね、楽しみを見つけたり、喜びを見出したりしなきゃいけないの。
ムチでひっぱたかれた「走り」は最初に加速をつけるには有効だけれど、ずっとは無理なのよ。
だって一生懸命走ってても、前を見ないでずーーとムチのほうを見るようになるからね。で、あるとき思うのよ「こいつ、オレ走ってるのになんでずっと尻ひっぱたいてんだ!?」ってね。疑問に思い出したら走るのがバカらしくなっちゃう。
だから、どこかでノリノリになったあととかひと山越えたところで、自分で「よっしゃー!」とか「いくぞー!」とか「いけるでー!」と思えないと、目の前の勝負に勝っても3年後には途中下車になっちゃう。
ゆっくりでもいいんです。走り続ける前提で考えていかなくちゃ。その走り続けていく過程で、頑張って前のめりになるものが子供たちが見るもの、触れるものに関係してくる。親や周りが与えるもの、見せるもの、触れさせるものに関係してくる。
たとえば「植物が花を咲かせるしくみ」がおもしろいと思える子供は科目としての生物は「勉強」じゃなくなる。義務でもなくなる。やらねーといけないものでもなくなる。自分の時間を割いてでもやりたいものになるからです。
それがどういうことかよくわからない人、また子供にとって勉強が勉強じゃなくなるってことがあるのかって信じられない人はこの本を手に取ってみるとイイです。
競争なしで一人勝ちできる。人生が逆転する秘密の勉強法
古本で今の時点で50冊ほど安く出ているので騙されたと思って読んでみてもいいかも!?
真の意味での「成績がイイ子」の様子ってこんな感じというのがよくわかります。もうね、やっていることが勉強じゃなくなるんです。
下世話な例でいえば、歴史で一生懸命年号覚えなくても、流れがわかっているから、時間が経っても忘れないし、相関関係がわかるから答えが出ちゃうし、こうなったのってどうしてだろうって疑問まで湧いちゃうからね。
もうこうなったら「勉強」じゃなくなっちゃうんですよ。「勉強」でしてたら忘れちゃう。だから忘れないような工夫をしなきゃいけない。時間も使わなきゃいけない。それが普通だし、そうすることを親技ではオススメしています。
でも、もう一歩先には興味を持って知るから「勉強じゃなくなる」境地っていうものがある。世間ではそういう人を天才って呼ぶ傾向にあるようですが、本人はそんな感じは全然もっちゃいない。
難しい問題見て「ああ、わかんない、やだー」となるのが普通なんだけど、「なんでそう聞くの」「なんでそうなるの」「そういうことか」「じゃあこの場合は・・・」って自分のほうに引き寄せて考えられる子供がいる。
そういう子供はね、1回見たらもう忘れないの。1回聞いたら頭に入っちゃう。聞いたり見たときに自分のほうに、自分の土俵に引き寄せて頭の引き出しに整頓して入れちゃうから。
その感覚ってどういう感じなの?っていうのをちゃんと言葉にして書いてくれているのが荒俣宏さんの「0点主義」。
ストロングも今のこの47歳のまま中3とかにワープできたら、できそうな気がしています。大人はみんなそうなのかもしれませんね。まあ、むなしい夢想ですけどね。
さあ、あなたはなにを子供に触れさせて、なにを見せますか。なにを与えますか。どんな体験を味あわせてやろうとしますか。47歳になってからじゃ遅すぎる。
今なんですよ、子供たちはね。
これって夢のあるクリスマスに考えるにはもってこいの話ではないでしょうか。
[30点UP] メンバーさんからの報告
中2 めざせ二ケタさん
◆報告内容:30点上がりました!
ストロング先生、こんにちは。私立中高一貫校中学2年男子の親です。
「30点上げよう会」に10月に入会し、2回の定期テストを終え昨日成績をもらってきました。
結果は、的をしぼった代数で、
1学期・中間42点⇒2学期・中間78点
1学期・期末37点⇒2学期・期末90点でした。
まずは、2学期中間テストをもう一度やりABC問題に分けたところ
A問題20%
B問題80%という結果に。親子ともとてもショックでした、できる問題ばかりだったんだと。
それを踏まえて子供と話し合い、学校では単元導入部分の説明はさほど詳しくなされず、それは知っている前提という事でしょうか、進んでいく。
ただ、今のレベルは取り戻せる内容(私から見てという、全く頼りない判定ですが)という事がわかりました。
期末対策として、教科書の単元導入部分から読んで演習をやり、そこでも問題をABC分類分けをしてABで間違えた問題は繰り返し、Cはしつこく追いませんでした。
一通り済ませた後は、学校から配られた期末用プリントを、C問題2問は深追いせず、AB問題のみ1週間前までに繰り返し。
間違えた問題は、どこでなぜ間違えたかを考え、半分の時間でできるまで繰り返し、前日にもう一度やり直しようやく90点まできました。期末もあと10点はなぜ落としたか、を考えやり直しをいたしました。
この3か月弱一緒に勉強時間を過ごしましたが、子供の表情、態度、話す内容が変わってきてとても喜んでいます。
中高一貫校は(特に地域柄)色んな意味でトップを自負するご家庭の子供たちが集まり、そこで何でもない自分を思い知って自信を失いかけていたように思います。
やれる自分を知ったのか、やればできる自分を信じられるようになったのか、とても落ち着いてきました。モチロン中学2年生らしい反抗はいたしますが、勉強は別と感じているようです。
ストロング先生には、ノリ勉数学で、中学3年夏まで(高校内容に入る前)が重要、中学受験の時と同じエネルギーで向えとメッセージを戴きました。
先を想像できない母でしたが、そのお言葉を信じ進んでいこうと思います。
子供の学校は、高校2年から習熟度によりクラスを振り分けられます。
もちろん下のクラスでも浪人すれば国公立、難関私立に合格していきますが、経済的な事も考えてやはり国公立現役合格を願っていますので、上のクラス入りというのは不可欠のようです。
振り分けは高校1年の実力テスト(と定期テストが少し)の成績のみです。ここからは目標を上位クラス入りとし、そこまでの決まりを設定する話し合いをします。
今更ではなく、ここからどうしたらいいか、考えて参ります。これからもストロング先生を頼りにしています。よろしくおねがいいたします。
「教科書の単元導入部分から読んで演習をやり」これが勝利の大きな要因でしょう。
教科書ができなくてチャートもプリントもできるか!ですな。
学校のシステムを理解し、足りない部分は自分たちで補うしかない。基本をやることを恥ずかしがる必要はない。遅れ始めた教科は特に注意したいところです。
目の前の小テスト、単元テストにかじりついて行け!です。日々の復習は欠かせない。ノリノリにして授業の受け方、ノートの取り方に意識が向きはじめると良い循環が生まれます。
中3になれば高校内容が入ってきて予習も欠かせなくなるでしょう。
「やれる自分」「やればできる自分」の実績と成果の一端は出た。その実績と成果を信じてとにかく目の前のことにかぶりつけ!冬休みは今までの復習に時間を使う。
中高一貫校の分岐点は高校内容が入ってくる中3の夏なり!