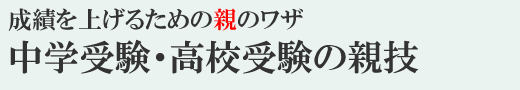先日、ネットのニュースをみておりましたら、裁判員制度に関するこんなニュースがありました。
裁判員制度は平成21年5月21日からが始まりました。その趣旨は、国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなる、司法に対する国民の信頼の向上につながるなどが期待されて始まりました。
裁判員制度が子供の勉強になんか関係あるの?
まあまあ、だまされたと思って読んでみてください(^_^)
きっとイイことありますから!どうぞ!
裁判員制度で、最高裁は
証拠調べの内容をメモに取らずに審理に集中するよう、
裁判員へ呼び掛ける必要があるとした報告書を取りまとめた。
メモに集中するあまり、法廷でのやりとりに意識が向かわず、心証形成がおろそかになる事態を避ける狙い。
裁判員が法廷でメモを取ることは自由だが、最高裁は有罪、無罪や量刑を決める評議の場では、法廷で撮影した録画を再生することで、裁判員の記憶を補うことにしている。
報告書は、これまでに全国で行われた模擬裁判で、裁判員役がメモに集中している姿が多く見られたと指摘。
裁判官3人と裁判員6人の全員が下を向いてメモを取っていた事例も挙げ、「『目で見て耳で聞く審理』の裁判員裁判では、正常な事態とはいえない」とした。
このため、裁判官が裁判員に対して「メモを取らなくても分かるような審理が行われるし、完全に覚えられなくても録画で確認できる」と事前に説明した上で、できる限り目の前の証拠調べへの集中を促すべきだとした。
さて、いかがでしょうか?
イイことありました?
というより、参考になるヒントが見つかりましたか?
この記事を読んでボクは大きく頷いたわけです。ここに出てくる「心証」という言葉、なんとなく意味が分かっても言葉の定義がわかりにくかったかも知れません。
『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』によれば、
心 証(しんしょう)
人の行動や言動が心に与える印象。
【法律】審理において裁判官が抱く認識や確信。
とあります。
これを踏まえて、記事を少し言い換えると、メモに集中するあまり、法廷でのやりとりに意識が向かわず、審理において裁判官が抱く認識や確信の形成がおろそかになるということになるでしょう。
この記事を紹介したのは、もうお気づきのように、子供たちが授業を受けるときの姿勢・態度をイメージしたからです。
もし、すでに授業を受ける我が子をイメージしていたなら、あなたは、なかなかの親技の持ち主とお見受けしますぞ!
学校でも塾でも、授業中ずっと下を向いてノートを取っている子供たちが多くいます。
ノートについてはこれまで幾度か取り上げてきましたね。
以前紹介もしたこともありますが、ノートの取り方の本も多く出ていますし、
きれいなノートには誰しも一度や二度は憧れるものです。
確かにメモやノートを取らなければ、すべてを記憶することはできません。だから、マジメな生徒ほど一生懸命ノートをとる傾向があるでしょう。
でも・・・というわけです。
メモに集中するあまり、授業でのやりとりに意識が向かわず心証形成がおろそかになる
裁判における「心証形成」がどのようなものかをボクは知りません。
が、授業においての「心証形成」は実は成績がイイ悪いの大きな分岐点になっているんじゃないかと思います。
この記事を読んで、ふとタイガー山中の授業風景を思い出しました。
タイガー山中の授業での口癖は、「ハイ、ペンを置いてこっちを見て!」
タイガーは自分が説明するときには必ず顔を自分やホワイトボードに向けるよう指示します。一人でも下を向いていたら、説明を始めないんですなあ。
まあ、性格がワガママだからといえば、まさにそうなんです。ワガママな先生に当たるなんて、生徒たちがかわいそ~(>_<)
ちなみに、タイガーは板書しながら説明するときも生徒には背中を見せません。体の正面は生徒の方に向けたまま、なんとも器用に板書していきます。
「○○、手を置いてこっち見るんやろ!」
おいおい、板書しながら生徒見てたんかい!目が後ろについてるんかい!って(◎_◎)
まあ、なんともピリピリした雰囲気・・・で授業は進んでいくんですな。
ただですね、実はこれこそが授業を受けさせて成果を出す秘訣であることを知らねばなりません。
ノートを取る必要はないということかって!?
いえいえ、そうではありませんよ。
現にタイガーの授業では、説明した後に必ずノートを書く時間を与えるわけです。
どんな様子かは想像できますよね(^_^)
「はい、じゃあ1分な!よ~い、ドン!」
みんな一斉に書き始めます。たった1分じゃあ板書なんて見る時間なんてありませんよ!
実は、そこにもタイガーの思惑があるわけです。
説明を聞く→ノートを取るの流れの中で、ノートを取る時間を制限する。
狙いは何か?
生徒たちは説明を聞きながら、板書の内容を暗記していかねばならないわけです。ただ板書を写していたんじゃあ、間に合いませんからね。
だって、時間になれば次の説明になるわけですし。そうなれば、生徒は手を置くしかありません。なので、生徒も必死です!
説明が終われば、ノートの時間がくる。だから、ある程度、内容を覚えておかねばと集中する。
問題だけじゃなく、解答までを順序だてて。
時々、タイガーの授業を生徒と同じように机に座って一緒に聞いていますとですねえ、時間内に書き終えた生徒たちはタイガーに勝った気になるんでしょうね。
様子を見ていると、無言ですが優越感に満ちた顔をしています。どんなもんだ!ってね。
みんなが時間内に書き終えるとタイガーも満足気です。そして、次の問題の説明がはじまる。
一通りホワイトボードで説明が終わると、説明を書いた横に類題を書いて、タイガーは言います。
「ハイ、じゃあ、ノートにこの問題を解いて!」
こうなると気の利いた生徒が必ず声を上げます。
「先生、何分?」って。
「そりゃあ、時間は1分やろ!ドン!」って。
タイガーの狙いはもうお分かりですよね?
ハイ、説明を聞く→ノートを取るではなく、
説明を聞く→理解する→解けるようになる
を授業内で生徒に求めるわけですね。
なぜこんな話をするかというと、別にタイガー山中の授業を褒めてるんじゃありません(^_^)
ボクの授業のほうが絶対におもしろいし、イイ授業だろって思ってますもん!この決着はいずれどこかでつけるつもりです、ハイ!
それはさておき、授業中、生徒たちは、
みんな一生懸命なんです(基本的には)。
ただ一生懸命にも、いろんな形があって、
◆ノートを取らず熱心に授業を聞いても一生懸命
◆ずっとを下を向いてノートを取っても一生懸命
なんです。
「今日は授業ちゃんと聞いたか?」って親が聞けば、「ウン」って子供は言うでしょ?
デタラメな塾ならいざ知らず、たいてい生徒は授業では一生懸命。ですが、親が考えておかねばならないのは、果たしてなにに一生懸命なのか?ということなんです。
実は、ノートを取るのに「一生懸命」かも・・・です。
もっと踏み込んで言うと、「熱心に授業を聞く」も
◆ただ熱心にうなづきながら聞く
◆熱心に聞きながら、こういうことなんだなとか、こうなったら、どうなんだろうと考えながら聞く
の大きく2つがあります。
今この同じ授業を聞くでも、どうしたら考えながら聞くように親ができるかをタイガー山中とあれこれ検討をしている最中なんです。
親ならだれでもできることになれば、発表したいと思っているんですが、これがなかなか誰にでも適用するのが難しい・・・
ボクなんかは「ただ熱心に聞く」タイプでした。「一生懸命」聞いていた。
タイガー山中は「考えながら、これはどうなんやろ?」と考えながら聞くタイプ。この考えながら、自問自答しながら授業を聞くタイプの子供だと、復習がものすごく楽になります。
一方のボクのタイプだと、熱心に聞いて帰っても、家に帰ると途端に解けなくなってしまったりする。
もちろん、タイガー山中タイプも全部が頭に入って帰るわけじゃない。だから、復習はいるんですが、それでも1から復習しないといけないボクのタイプよりも圧倒的に短時間で処理できる。
同じ「一生懸命」でも違うってことです。
家であまり勉強していないように見える成績がイイ子供たちは、授業中に頭の中をフル回転させている可能性が高いです。
つまり、同じ一生懸命でもずっと下向いてノートを取っている子供は復習に時間がかかりやすい。
同じ「一生懸命」なのに・・・・
頭の中は見えないから、頭の中がどんなふうになっているかはわかりません。でも、確かに授業を自問自答しながら聞いている子供たちはいます。
そういう子は授業の中である程度「落とし込み」ができるから、家に帰ってからが早い。
その感覚は伝えるのは難しい・・・・です。
でも「一生懸命」にも中身があり、違いがある。そのことを知っておいてほしいのです。
塾から戻ってきたらノートを見てみる。きれいに書いてきてるからといって安心しててはダメ!
ノートは、理解して書いたのか、それとも説明もそっちのけでただ板書を書き写しただけなのか?
後者であれば、ノートは必要ありません。ノートの代わりに頭の中に書き写して帰ることを課題にするのです。
前に何度か書いたことがありますが、塾からの帰り道に授業で習ったことを子供に説明させる。最初はうまく説明できなくても、うまく説明するために授業を聞くようになればいい。
説明もしっかりと、しかも長く続くようになったとき、家庭での復習の時間は今より短縮できるでしょう。
大の大人だって、なにがしかの重大な結論を出そうとすれば、メモに集中するあまり、法廷でのやりとりに意識が向かわず、心証形成がおろそかになる
のです。
大人なら言われたらわかるけど、子供は・・・・
授業において子供が抱く認識や確信を高める方法は今のところ、そういう授業をしてくれる先生やできていなければ指摘してくれる先生を選ぶか、家に帰る途中や家に帰って親がいかに問いかけるかにかかっているでしょう。
また、実際に私たちも試しにすでにやってもいますが、社会は机に座って勉強しない。授業を聞いて、あとは空いている時間に立ってやるなど、親の子供への要求を変化させて、授業のお土産をいかに増やすか。
ただ「授業をちゃんと聞いてこい」では解決しない問題です。
だってみんな「一生懸命」だから。
その「一生懸命」の中身を家庭で親がどう問うていくかが今すごく求められていますし、それぞれの子供でやり方が全部違ってもくるでしょう。
それを真剣に考え、トライ&エラーしている子供が「楽」ができる。「楽」をして成績がイイとなる可能性が高いのです。
子供が頑張るだけではなく、授業を受け持つ先生の影響も多々ありますが、ぜひ授業を受けたあとでお子さんに授業内容を問いかける試みだけは続けてほしいと思います。
決して立て板に水の説明を求める必要はないのです。子供が自分の頭の中にあるものをいかに言葉で紡ぎ出させるか。
そうすると、「聞いてもおもしろかったとかしか言わないんです!」という親がいることでしょう。
親として「どうだった?」「何習った?」しか問いかけなければ、「おもしろかった」「よくわかった」「和差算」としか返ってこないでしょう。
子供の「一生懸命」とともに親の「一生懸命」もその質が問われているのかもしれませんね。
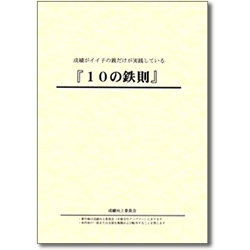
成績が上がらない理由を子供のせいにしていたのでは何も解決しません。成績は、親次第で上がりますから!
対象:就学前、小学生、中学生の親
・親にできることは何かを知りたい
・今の問題は何かを知りたい
・成績がイイ子の親が何をしているのか知りたい