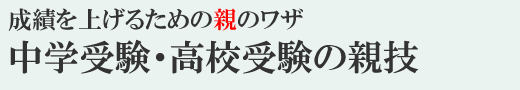以前のメルマガで中3の息子さんが自習室に閉じこもり、親技を発揮する時がないというものがありましたが、うちはその逆を相談したいと思います。
小5の息子は、小さい頃から私がそばで勉強をみてきたためか、自分からは勉強をしようとはしません。
やはり私にも時間の制限があり、今はみてやれない、でもあいている時間に自分で勉強してくれたらもっといい点が取れるのにと思うのです。
つまり、私との勉強時間だけでは足りないと私は思うのです。
これをやっててね。という風に指示をだせば、やってくれる時もありますが、どうやったら自分から進んで(何をするか指示なしで)勉強するようになるのでしょうか?
明日がテストでも「やらなきゃ!」という危機感があまりないようなのです。これって、初歩的なことができていないってことで、お恥ずかしいのですが、この際なので、相談します。
親がそばにいれば勉強するけど、そばにいないと勉強しないというお子さんについての相談です。
よく「一緒に勉強しようとしてもすぐにバトルになって勉強になりません」なんて相談も届きますが、ミッチーさんの場合はそうではないんですね。
でも、ミッチーさんの場合は、
自分からは勉強をしようとはしません
だそうです。
1つクリアすれば、次の課題。親の要求はどんどんエスカレートします。
欲深いですねあ(^ε^)-☆
でも、明日がテストでも危機感がないとありますから、見ているほうはやっぱり困る。いくら勉強をそばで見ることには抵抗しないからといって、これじゃあ・・・・と思いたくもなります。
やっぱり原因は、小さいころから親が勉強を見ていると、自分で考えない子供になってしまう!なのか?
やっぱり勉強は自分でさせるべきだし、親が口出しするのはおかしのかも・・・・
塾の先生から「親が家で勉強の口出しすると合格できませんよ!」とか「子供の自主性を尊重しないと中学生になってから困りますよ!」と言われたなんていう相談が1ヶ月のうちに必ず何通かあります。
ストロングは「親が・・・」って言うし、
塾の先生は「子供の自主性を・・・・」と言う。
で、私はいったいどっちを選択すればいいのか?というわけです。まあ、それぞれの考え方ですから、どっちを選択してもかまいません!
それは親がそれぞれ決めればいい。
ただストロングは、これまでの経験から、子供の自主性に任せていたけど受験まで尻に火がつかなかった!
もともと成績がイイ子供は別にして、段々と徐々に成績が上がっていく子供の親は家庭で勉強を見ている!
ということから、そばで勉強を見たほうがいいですよと申し上げている次第です。
そりゃあ、ボクだって、塾にさえ子供を行かせれば、子供の自主性がグングン育って、成績がガンガン上がるなら、そんな塾に我が子を行かせたいです!
塾へ行って授業さえ聞いてくれば、ちゃんと理解して、問題も解けるようになって帰ってくれるなら、多少月謝が高くてもずーーと子供を預けたい!
でも、多くの子供たちは、自主的に勉強はしないし、すぐわからないと言うし、授業で習った問題ですら???な場合も多々ある。
少し話がそれていますが、親がどうかかわるべきかというのは、悩む問題ではなくて、決断の問題です。
我が子を見て、もちろん兄弟姉妹でも違いますから、決めてください。
決めたら、目一杯かかわる。
又は、塾におまかせする。
結果はテストや受験や時間が経過する今後にわかる。
この日本中、どの子供もみんな生まれたときから今まで環境も育ち方も全部違うんです。答えが1つということはない。
えっ、兄弟は育った環境も親も育て方も基本的に一緒だって!?
ホントでしょうか?
ストロングは違うと思います(皆さんの考えは違ってもいいんですよ)。
環境だけとってみても、第1子が生まれたときと、第2子が生まれたときは家族の状況が全然違います。
年子なんかだと第1子と第2子で子供にかける時間はメチャクチャ違うでしょう?
初めての子育てと2番目は経験していることも違うし、間違いなく下のお子さんのほうが要領は良くなっているはずです。おじいちゃんやおばあちゃんの扱いもこれまた違う。
というように、誰一人子供たちはまったく同じ育て方をしているという子供はいない。だから、違って当然。
であるならば、親のかかわり方も違って当たり前。
ミッチーさんの相談に話を戻します。
親が子供の勉強にかかわらなければ、自分で考えて勉強する子になるのか?
答えは、限りなく「ノー」に近いでしょう。
親に言われなくても自覚を持って勉強する子がいるのは事実です。親にとっては、夢のような話。
そんな他人から見れば憧れの存在の「自覚を持って勉強する子供をもつ」親のみなさんが苦労されるのは、下のお子さんなんですから。
「上の子供のように黙っていたら、下の子は何もしなくて・・・」なんていう相談がこれまたストロングによく届きます。
同じ塾に通って、先生も同じ、親も同じ。なぜだーー!?というわけです。でも、それが普通なんです。
つまり、
最初から、自覚して勉強するなんて期待すべきでない
ということです。
自覚してやる子供であればラッキー!でも、そうでなかったら、普通!ですからね。
それを前提の話ですが、それでも、ミッチーさんのような状態であれば、やっぱり問題だと思います。
親が見てやれない状態で
明日がテストでも、やらなきゃ!という危機感があまりない
この状態では、現状の成績からは上がりませんから(>_<)
では、どうやって子供たちを自覚して勉強に取り組むようにさせるか?
これが、ちとやっかいなんです(>_<)
子供が親に頼りきっている家庭の共通点として
「親子の役割分担が、うまくいっていない」
という点があげられます。
どういうことか?
それは、
親ばかりが役割を担っており、子供の役割が明確でない
ということです。
よく親が子供の勉強にかかわると、子供を甘やかしすぎだと批判する方がいますが、甘やかすことには断じてなりません。
だって、親がプリントの整理などを手伝ってやる代わりに、子供は勉強することに専念させるわけです。
子供にとっては大変です(◎_◎)
親が勉強の習熟度を考えながら計画を立て、子供は予定通りに勉強をしていく。
プリント整理したり、ノート作っている時間、これを子供は勉強時間に換算しますが、これって休憩と同じですから!
↑↑こっちのほうが断然甘い!
そうやって、親の時間を割くことで、子供の限られた時間の中で、勉強の効率を上げることで成績を上げていくわけです。
親がいくら頑張っても、子供は自分が何をするかがわかっていない。これでは、親の頑張りは「無」になってしまいます。
そこで、ミッチーさんには、お子さんにこう聞いてみてほしいものです。
成績を上げるために、お母さんにしてほしいことはなに?
「えっ」とたぶん驚くでしょうから、今までミッチーさんが担当してきたことなどを
1つ1つ「これは、すべき?」と聞いていくのです。
これを1つ1つ紙に書いていきます。細かく書いていけば、10コや20コはあるのではないでしょうか?
もし、新たに追加して欲しいことがあれば、それも書きます。次に、子供の番。
成績を上げるために自分がすることを話し合います。子供も同じように書くわけですが、紙にはたった1つ
「勉強する」
だけになるかもしれません(^_^)
そこで、今度は
次のテストに向けて、お母さんにしてほしいことはなに?
と紙をさして尋ねるのです。
これは、次のテストに向けての役割分担を決めていく作業。
ここでのポイントは、
「一緒にすること」
「担当を返上すること」
などを決めることで、ミッチーさんの分担を減らすことにあります。
子供に対して「自分でやれ!」と分担を放棄することではなく、お互いの役割を確認することですから
「これは一緒にやろうよ」
「これは自分でした方がいいかもね」
といった感じで進めていきましょう。
もちろん、子供が「自分ですること」については、取り組みやすい課題にさりげなくしておくのは親技です。
例えば、親と一緒にやって、できた問題を時間を計ってもう一度やるとかね。
そうしないと、難しい問題やややこしいものを「やっておきなさい!」では、子供はやる前から心が折れてしまいますから。
できそうなもの、確実にできるものを「自分ですること」にまずしてみる。やっていたら褒めてやることができます。すごいねって!
ああーーーー、手間がかかりますなあ・・・自主性を求めていくのも。
でも、これを惜しめば・・・とよく考えてください。
いいですね?
お互いに納得した上で役割を決めたら、次のテストに向けて勉強を開始です!
あと、弟や妹がいる場合に効果的なのが、
お母さんごっこ(^_^)
弟や妹の勉強をお母さんの代わりに見させるのです。期間限定で、自分がお母さんやお父さんからしてもらっていることを弟や妹にするのです。
勉強の準備を手伝うのがどんだけ面倒くさいかということや集中して勉強しないことでそばにいる者の時間までを無駄にしてしまうことなどを体験することになります。
弟や妹に「問題をよく読んで!」なんてね。
同じ立場では気づかないことでも、立場が代わることで見えてくることだってありますから。
そう簡単に自分から勉強をするようにはならないものですが、親子の役割分担を確認する作業は定期的に行うとよいでしょう。
以前に比べて、自分でできるようになっていることが増えていれば、よくなっているということですし、それをお子さんにもきちんと事実として話してあげられます。
「自分一人でやること」というと、かなり漠然とした大きなくくりになります。
その大きなくくりのものを丸投げして「どうしてできないの?」では、チトお子さんがかわいそうです。
ぜひ細分化してやってみてください。
自分から勉強する習慣をつけることは、更なる成績アップにつながりますし、授業を受けてきたときのお土産、つまり理解して解けるようになって帰って来る問題も増えますから。