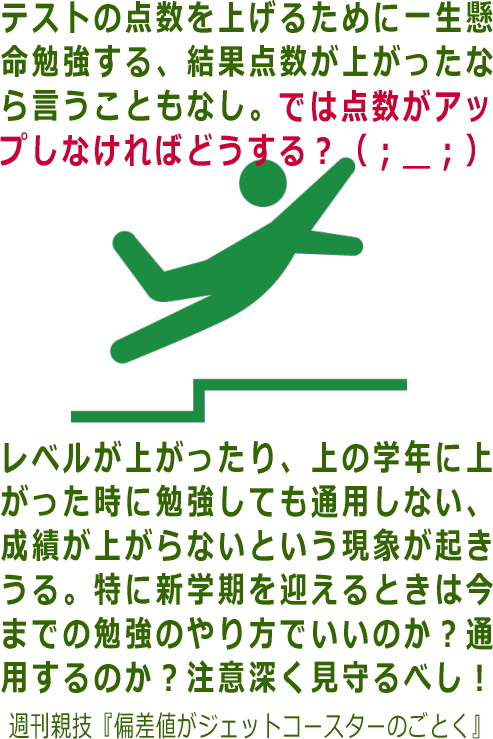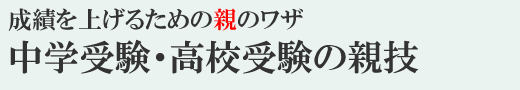早速読んでいただいて私のバズーカ砲を受け止めていただきましょうか。
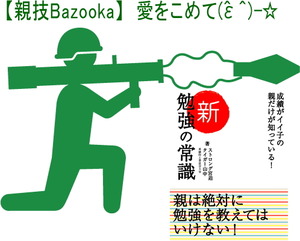
まずはいただいた報告を読んでいただきましょう。
小4 リハビリママさん
テスト名 = 塾内模試
点数報告 = 合計29点アップ
国算合計125点 → 国算合計154点
偏差値は7.3アップ。
国算偏差値合計47.2 → 国算偏差値合計54.5
素点で29点UP!偏差値で7.3UP!
成績が上がったという報告は、ストロングにとってなによりのご褒美ですから、思わずニンマリ(^_^)
しかし、最後にこんな報告が・・・
模試を比較すると、とても上がっているようですが、実はこの1年間は偏差値がジェットコースターのごとく上下していまして、47から56をいったりきたりしております。
できれば56以上を5年からはキープできればなぁ、と思っています。
アチャー(>_<)
テストの点数は、前回の結果が悪ければ、次のテストは当然、点数は上がりやすい。上がったというよりは元に戻ったとも言えるし・・・・点数が上がっては次に下がって、また上がったの繰り返し。
これは復テ対策講座や30点上げよう会でお話しているのですが、
こんな状態を
「ムラムラ型」
と親技では呼んでいます。
もちろん、親としては取れることが証明されている「良い状態」をキープしたいと考えますよね。そこで、リハビリママさんは、もちろん!!塾の先生に相談された。
問題や悩みがあれば相談する!これ基本です。
すると、塾の先生は
年齢が小さいので、テストで舞い上がってしまうのでしょう。
内容はよく理解しているので(多分、応用問題を解いているのでこう言われたと思います。)5年生になれば落ち着いてきて、成績が安定します。
と言われたそうです。
ほーー、なるほどなるほど。
どうですか? ちょっとは、安心しましたか?
もし、塾の先生にこんな風に言われて安心だと思った方はかなりヤバイです(>_<)
ストロングは、塾の先生の言うことを信用するなと言ってるのではありません。でも、言われたことを全て鵜呑みにしてはダメだと言っているのです。
だって、この塾の先生の見解がもし間違っていたらどうします?
5年生になって今よりももっと成績が乱高下したりしたら?
ストロングの経験では、その可能性は十分にあります。
だから、なにか言われたら、必ず
なぜ、そう断言できるの?
という問いかけを常にすべきなのです。
これは、誰に対しても、もちろん、ストロングの言うことに対してもですぞ(^_^)
そうすることで、いろいろなことに応用が効くようになってくるし、様々な場面に的確な対処ができるようになる。
さて、塾の先生は、リハビリママさんに
今は小4だからムラムラ型だけど、小5になったら成績は安定する
とのアドバイスした。
これに対して、みんな同時に小5になるのに、いったい誰の成績が落ちるんだろう?ぐらいの疑問は持つべきです。成績(偏差値)が上がるということは、誰かの成績は下がることを意味します。みんなが同じ勉強のやり方を続けて、あるものは上がり、あるものは下がるなんておかしいのです。
また、小4で乱高下している成績が、内容も量もレベルが上がる小5になって、なぜ安定するのか?という疑問を持つべきでもあるでしょう。単純に小4から小5になれば、授業時間は倍くらいにはなる。
小5になってレベルが上がれば、成績が乱高下するのは同じにしても、小4のときの最高偏差値56はでなくなる可能性だって十分あるわけですから。
リハビリママさんはそこはハッキリと感じておられたようで、いただいた報告には、塾の先生のアドバイスに対して
「心もとないアドバイス」
とありました。
実際のところ、ストロングが塾で教えていたときは、ストロングも似たような答えをしていたと思います。
「まあ、大丈夫ですよ!」なんて・・・・
では、今はなんと言っているか?
成績が乱高下するムラムラ型を脱して、好成績をキープできるかは「親次第」とストロングは思っています。
なぜなら原因があるからです。親次第と言っても、日々、子供のそばについて勉強するだけでは、この問題は解決しません。そばで子供の勉強を観察して、状況を把握して、次の一手を考える、そういう親技が必要になります。
その状況を把握するための1つの方法として、ABCテスト分析法があることは何度か紹介しましたので、皆さんもよくご存知だと思います。
ABCテスト分析法
https://www.oyawaza.com/abcin.htm
この方法は、
子供の勉強の状況を把握し、その分析結果から、対策を決める
「親技」を駆使するための1つの方法です。もちろん、最初からは無理です。親もトライ&エラーを繰り返しながら、精度を上げていく。
リハビリママさんの場合は、状況を把握する「親技」はすでに習得しつつあります。さあ、ここからはメンバーさんにとっては、復習の内容ですぞ!自分で答えを言いながら、読み進めて下さい。
リハビリママさんの今回のテストについての分析は以下です。
今回は前回よりも本人にとってやさしい問題が多く、ABC分析を行うと、
算数 A問題は25/30 B問題は3/25 C問題は2/25
国語 A問題は39/48 B問題は6/48 C問題は3/48でした。
正答率は、
算数 A問題84.0% B問題66.7% C問題0.00%。
国語 A問題94.9% B問題66.7% C問題33.4%でした。
そうです、偏差値の足を引っ張っているのは、算数のA問題。今回はA問題でミスをしてしまったようです。基礎問題の練習量が足りなかったのかなぁ、それとも浮き足出ってしまったのかなぁ、と考えています。
とてもイイ点の取り方をされつつあるのがよくわかります。
こうやって地道にテストが終わったら分析して、なんとなくではなく、キッチリと把握することで、次の対策は自ずと見えてくるわけです。
ストロングは、リハビリママさんにこう書いて送りました。
これはムラムラ型というものであるとストロングは認識しておりまして、テスト勉強の取り組み方によって、そうなっていくと推測しております。
取り組み方とはABCの順番の問題です。つまり、いかなる単元であってもまずはA問題を撃破する。いただいた今回のテスト結果分析を見ると、勉強の取り組み方のバランスは総じて良かったと判定できます。
次回のテストでは、A問題の正答率を90%以上にするのが最優先。B問題の正答率をもう少し上げるのが次善の策となるでしょう。
今までのテストを分析したらはっきりと出ると思いますが、ムラムラ型の場合、A問題の正答率が乱高下しているはずです。その代わり、C問題の正答率が高くなっていたりもする。つまり、勉強の優先順位がバラバラになっていることがムラムラ型になる原因です。
そのことを念頭に、次回以降やっていったらいいと思います。今回の勉強はいいテスト勉強をしたのです。次回はもっとA問題の精度を上げる。そうやっていけば、テストの点数は安定してくると思います。頑張ってください。
と。
「テストの点数を上げるために一生懸命勉強する」これはもっとも大事なことですし、これについて異論はないでしょう。そして、一生懸命勉強をしてテストの点数が上がった!であれば、それ以上文句のつけようはありません。
しかし、一生懸命勉強しても、その勉強のやり方、勉強の中身によっては、上の学年に上がったときに通用しなくなったり、一生懸命勉強しても成績が上がらないという現象が起きます。
一生懸命時間をかけて勉強したのに、通用しなかったり、点数がアップしなければ、どうなるか?
そのとき、子供は「自分の能力がない」とか「周りがすごい」とか「頑張っても意味ない」とか言います。でも、そうじゃない。勉強のやり方、取り組み方をもう一度考える余地があるわけです。
そのことを言ってあげられるのは、果たして誰なのか?
一番確実に言ってあげられるのは親である、そうストロングは思っているからこそ「親が・・・・」と繰り返し言っているわけです。
これから新しい学年、新しい学校が始まります。今までやっていた勉強のやり方はいいのか?通用するのか?と、これを機会にぜひ考えてほしいと思います。今まで通用していたやり方がそのまま使える方は意外と少ないのですから。
ちなみにストロングは中学で好成績を取っていたやり方が高校ではまったく通用せず、高1の夏前にはすでに撃沈し、そのまま浮上できずに、2浪したことを付け加えておきます。
気づくのが遅すぎたのです・・・あーーー思い出したらせつなくなってきました。
一人でも多くの方にそのことに気づいてほしい。ストロングの分まで。そう心から願っています。