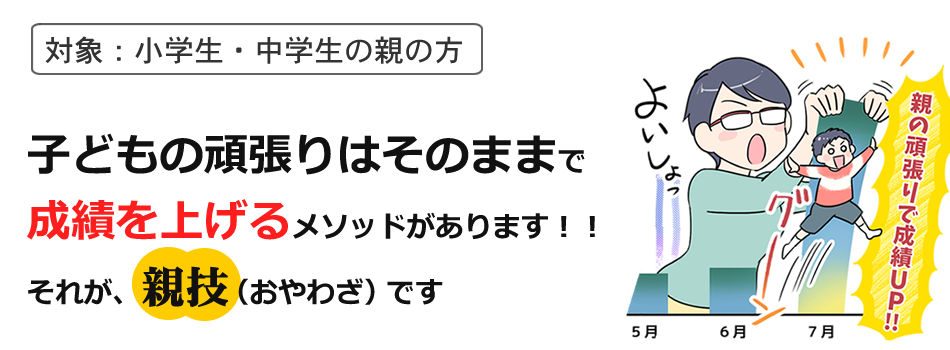「『これならやってもいいかな』と思えるようにしてやらせる」
『難しい問題』という大きな壁に直面した時は、その壁を細分化して、1つ1つイヤなものを取り除き、それほど面倒でも、イヤなものでもないよ!と思えるようにしてやります。
例えば、「これとこれだけやってみない?」と30分で終われそうな量を設定して、
考えなくてもイイよ!
答えを見てもイイよ!
ゆっくり解けばイイよ!
と子どもにとってイヤなものを取り除き、『これならやってもいいかな』と思えるようにしてやらせていきます。
親技では、この他にもちょっと変えるだけで「子どもの勉強がガラっと変わる」様々な工夫を紹介しています。

子どもの頑張りはそのままで、親の工夫や頑張りで成績を上げるノウハウを「親技(おやわざ)」といいます。勉強に関する様々な悩みを子ども任せにせず、親子で取り組んでいきたい方にお勧めです。
さて、ここからはもう少し詳しく「難しい問題集に取り組むためには?」というテーマで話を進めていきますね。
中2の娘のことを相談させてください。
子供は中学受験を経験し、塾に行かずに親子で勉強し、中堅に受かったが、「勉強量が足りなかった、合格したからには行ったほうがいいのは理解しているがどうしても行こうと思えない」ということで本人の意思で辞退し、公立中学を選択しました。
勉強量が足りなかった、という反省があるため、中学に入ってから親の介入なしに、すごく集中して勉強をしている様子です。
そのためか、定期テストでもいつも安定した成績で、クラスで2番か3番の位置におり、地域トップ校を目指すと張り切っています。
が、今日、全県模試を初めて受けて、愕然としました。
学校の定期テストでは点が取れている、しかし模試では取れない教科がある。きっと基本的なことはできている、しかし、、、
応用になると得意な数学ができていないんです。本人もかなりショックを受けておりました。
これまで、通信教材は小5から2種類辞めたりまたやってみたりして続けています。
1年の秋に英語がどんなに頑張っても点数が伸びず、どうしてもといって個別に入塾、得意科目になるまで鍛えていただきました。
2年からは、自分の力だけで頑張って成績をキープする自信がないのと、友人が行くからと、補習塾に通いました。
しかし、補習塾に行っても、行かなくても、点数は変わらない。本人もそれに気づき、楽しいけれど進学塾に転塾する決意を固め、夏期講習から進学塾に入塾予定です。
本人の性格上、そこそこのところで安心し、「ま、いっか」というツメが甘いタイプです。
通信の教材の添削が戻ってきても、できなかったところをできるようになるまで振り返ってやり直す、というところをおざなりにしてきてしまった事が、気になっております。
模試用の難しい問題集には手をつけたがりません。ささっとやってサラサラ解ける、そんな問題集が大好きです。
苦手なことからは目を背けていたら、模試や入試など、トップ校ねらいの子の中では太刀打ちできないのでは?
本人、気づきますかねぇ・・・
もう思春期で親がいっても却って反発するので、すごく難しい。
模試の答えあわせを一緒にやって、思わずできなかったところを指摘し、熱く語ってしまい、逆効果です。
時間をおいて、「あなたはよくやって、随分解けたよね!」というところを、認める方向で言葉をかけ直しました。(ため息)
こんな我が家の娘にアドバイスを与えるとしたらどんな方向からいえばいいのでしょうか。
中学受験をされて合格した学校には進学せず、地元の公立中学校に通っていらっしゃるそうです。
受験が終わりよくいただく相談として、「合格した学校にいくべきか、地元の公立中学に通うべきか」というのがあります。
なので相談者さんの事例はぜひとも参考にしていただきたいものです。
入学する前の時点では、どちらの学校が本人に合ってるかなんてわからないものです。
調べても、学校訪問しても、どうしても入ってみないとわからないところがある。
また、我が子の適性を見誤っている場合もあって、バッチリと思って入学したら、こんなはずではなかった・・という場合もあります。
私立に進んでも一定の割合で退学・転校というのがあるのも、そのあたりが要因でしょう。
子供の意見を尊重してやりたいという親もいるでしょう。
親のススメで学校を選ぶことだってあるでしょう。
人それぞれ。答えはない。
ただ1点、
「せっかく合格した学校なんだから・・・」
こういう理由だけは私はおススメできません!
いろいろな状況を考えた上で「合格をもらった学校でもあるし」となれば問題はありませんが、「せっかく・・」が学校を決める理由の上位にきてしまっては問題です。
最終的には入学するまで、一定期間を過ごしてみるまでわからないにしても、
この学校は我が子には「この点については合う」
一方で「この点については合わない」
と挙げながら最終的に学校を選んで決めていく。
その過程がなければ、退学・転校の事態になったときでも、そこでの話し合いの過程が活きくる。
私が見てきた「うまくいく学校選び」について、
大変だと思う方を選択した方がうまくいく
こんなことが言えます。
本にも書きましたが、勉強は十分ついていけそうで余裕ありと思えるA校。落ちこぼれそうで心配なB校。
こういう選択の場合、B校を選択した人は基本的に落ちこぼれません。
理由は、あせって勉強するから(^_^)
もちろん、勉強だけに限った話ではありません。
校風だってそうですが、厳しいことを覚悟して選んだ学校を選択した人は結果的に成長するということだと思います。
相談者さんのお子さんの場合も「よい選択」をされたと私は思います。
勉強量が足りなかった、合格したからには行ったほうがいいのは理解しているがどうしても行こうと思えない
という反省から公立中学校を選ぶことは並大抵の決断ではありません(◎_◎)
その決意が、
定期テストでもいつも安定した成績で、クラスで2番か3番の位置におり、地域トップ校を目指すと張り切っています
へと導いてきたわけです。
ここまではバッチリですよね。
さあ、しかし、模試を受けて数学の応用ができてないことが判明。
本人もかなりショックを受けたそうです。
だったら、今度も!?っと思いきや
もう思春期で親がいっても却って反発するので、すごく難しい。
模試の答えあわせを一緒にやって、思わずできなかったところを指摘し、熱く語ってしまい、逆効果です。
となかなかうまくはいかないそうです。
諸般の事情から中学に入って
「親の介入なしに、すごく集中して勉強をしている様子」
ということですから、これまではお子さんにお任せ状態だったのでしょう。
となれば、相談者さんも本気でかからなければ、子供にはかかわりづらい状況だと思います。
だって普段は見ていないけど、悪い点数のテストが返ってきた途端、これはまずい!と
「できなかったところを指摘し、熱く語ってしまった」
わけでしょう。
そりゃあ、子供も嫌がります。
「うるせぇーなあ!」ってな感じなんじゃないでしょうか。
これは自分に当てはめてみれば、すぐわかると思いますが、ノータッチできたものが途端に眼の色変えて、それもズバリ正論を吐かれたとしたら、「ナニーー!」ってなる。
人間は、特に子供は感情の動物ですからね。
そういう意味で、今後受験までかかわるのか、それともかかわらないのか、その程度があると思いますが、そこをハッキリしておかないと、いざというときにはかかわれないということが起こりえます。
我が家の娘にアドバイスを与えるとしたらどんな方向から・・
は、相談者さんがどれくらいかかわるつもりなのかによって、大きく変わってくると思います。
相談者さん自身が
本人、気づきますかねぇ・・・
というあたり、まだ迷っている部分があるのでしょう。
確かに自分に厳しい選択をして、1年以上がんばってこられた子供ですから、今回だってまた頑張ればいずれクリアできるでしょう。
それもやらなきゃならないことも明確です。
なにかをキッカケに目覚めて「よしやるぞ!」となる場合もありますし。
しかし、メールで拝見する限り、補習塾などで心に火がつく可能性はそう高くなさそうです。
それに「苦手なもの」「わからないと思っている応用」なんかを自分にムチ打って課すことができる子供はそう多くないことも事実なのです。
繰り返しますが、今回の相談は、相談者さんがこれからどうかかわるつもりなのかがまず問われる相談です。
今のお子さんの状態は、「嫌なものは嫌!」でしょう。
ささっとやってサラサラ解ける、そんな問題集が大好きです。
これが勉強の第一ステップ。
これすらできない子供だっている。
それを相談者さんのお子さんは自分でクリアした。
次はできない問題へのチャレンジ。これ必然。
ノリ勉でいえば、第2ステップに位置付けているものです。
親のみなさんだって経験あると思いますが、
「わからない問題をわかる(解ける)ようにする」
という行為は非常にパワーが必要です。
大きな壁に直面した時は、その壁を細分化して、1つ1つイヤなものを取り除いてやるしかない。
「考えるのがイヤだ!」なら、考えなくてもイイよ!「見てもわかんない!」なら、答えを見てもイイよ!「早く解けないもん!」なら、ゆっくり解けばイイよ!
と。
最終的に子供ができるようにしていくわけですが、その過程では1つ1つイヤと思っているものを細分化して、
それほど面倒でも、イヤなものでもないよ!
ということを教えてやらないといけないわけです。
また、
模試用の難しい問題集には手をつけたがりません。
は、ごく当然で、子供が問題集を見れば、手のかかりそうなもの面倒なものばかりに見えるわけです。
ならば、「これとこれだけやってみない?」と30分で終われそうな量を設定して、
考えなくてもイイよ!答えを見てもイイよ!ゆっくり解けばイイよ!一緒に考えようよ!
と寄り添ってやる。
相談者さんのお子さんだってわかっちゃいるんですよ。
やらなきゃならない!
でも、できない・・・・・
本人の性格上、そこそこのところで安心し、「ま、いっか」というツメが甘いタイプです。
これでいうと、みんなそうです。
子供が管理して子供自身が勉強する場合、どうしてもツメは甘くなる。
だから、親がそばについて親技を駆使して、「やること」を管理するのです。勉強でもスポーツでも、選手自身は「キツイことをやっている」と思いたい。
自分は「頑張っている」と思いたい。
現に一定の時間を費やしている場合は、そう思える状況でもあるのです。
しかし、さらに上を目指すには、今の実力より少し上のことを課さなければ、勉強だってスポーツだって上達はしないし、上にはいけないわけです。
至極当然な結論です。
それを「なにを甘いことをやっているんだ。もっと自分を追い込め」と言われても・・・・自分では追い込んでいるつもり。
そういうことでしょう。
3度目の問いになります。
相談者さんはどういう形でかかわろうとするのですか?
子供自身で気づいて自分で負荷をかけてほしいのか?
それとも、まだそれは無理だから、親が伴走者として子供に少し上の負荷をかけるのか?
もし、子供のそばで負荷をかけるとするなら、トップ校を狙うための実力を今のうちに身につけておきたいと思うなら、相談者さんは考えないといけません。
いきなり飛び出て来て「なにやってるの!」と熱く語るようなことは逆効果。
今の実力を見極めて、30分。30分が無理なら15分。または模試用の問題集から1問だけ。
とこれならやってもいいかなと思えるものを選択して、毎日課していく。
それしかないでしょう。
面倒なんですよ、親技って!
苦手なことからは目を背けていたら、模試や入試など、トップ校ねらいの子の中では太刀打ちできないのでは?
ハイ!太刀打ちできません。
学校の定期テストと受験する学校の入試問題を見比べたら、それはすぐわかる。
入試問題のうち、今の段階ですでに習っている単元があります。
そこの入試問題をやれば、習ったにもかかわらず、全然解けない問題が結構あることに気づくでしょう。
問題の難易度は、
1定期テスト → 2実力テスト → 3模試 → 4入試問題
と段階的に上がっていきます。
相談者さんのお子さんの学校の休み明けの実力テストがいかほど取れているのか定かでありませんが、今は1の段階か2の段階です。
同じ模試でも中3になれば、複合問題になるので、さらにやっかいにもなっていくでしょう。
今、親が手を差し伸べることがあるとすれば、第一歩を進むための手助けをしてやることです。
もしかしたら、ハードルを下げてやって、一度進みはじめたら、自分で進んでいくかもしれません。
それはわかりませんが、可能性はある。
ならば、第一歩を一緒に歩んだらどうでしょうか?
上から目線ではなく、「やらなきゃいけないけど、なかなか手がつけられない、気が進まない」という誰でもが持っている感情を前提に歩む。
具体的には、先に書いたような手段を使って、ハードルを下げてやって、わからない問題を親子で一緒に解く。解説を一緒に見てみるとか。
「これはね、こうやって、こうで・・・」なんて言わずに、わかってはいても、「こうなんだ」「ヘェー」って言ってあげたらどうでしょう。
親の方が子供よりもわからないといった内容であれば、一緒に解くのがよいでしょう。
「お母さん、わからないの!?」
ぐらいが子供は一番盛り上がりますから。
また、それが難しいなら、課題を決めて自分なりに理解できたら、親に説明をするといった約束をしてみるのもいいでしょう。
やらなきゃいけないとわかっているけど、できないというのは悩みとしては上等な部類です。
中学に入ってからは楽をさせてもらってきたんです。
相談者さん、出番ですよ!!
子供に負荷をかけるんです。
正論とわかっていても、それを柔らかくして聞いてもらえるように努力するのは親の役目。
負荷を課すことができるのは、信頼関係がある人間だけなのですから。
1日に1題ずつでも構いません。
欲張らずに、0(ゼロ)より1を選ぶ作戦ですよ。

子どもの頑張りはそのままで、親の工夫や頑張りで成績を上げるノウハウを「親技(おやわざ)」といいます。勉強に関する様々な悩みを子ども任せにせず、親子で取り組んでいきたい方にお勧めです。