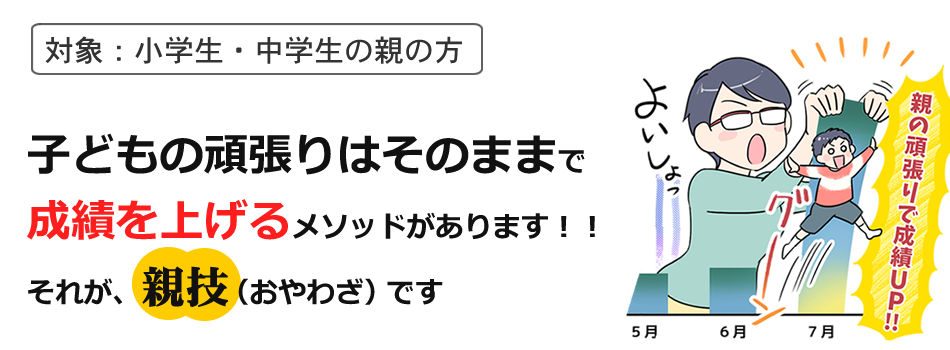「塾の先生の事情、心情を考えてお願いをする」
塾の先生に「今はやらなくても大丈夫ですよ!」と言われた場合、なぜそう言われたのか理由を考えてみます。
本当に必要がないのか?或いは一人のために時間を割きたくないのか?或いは・・・?
先生の事情、心情を考えたうえで、
「それくらいのことなら、やってあげられるな。」
「この親は熱心な親だから相談には乗らなくては。」
と、お願いを聞いてもらえるように仕向けることが必要です。

子どもの頑張りはそのままで、親の工夫や頑張りで成績を上げるノウハウを「親技(おやわざ)」といいます。勉強に関する様々な悩みを子ども任せにせず、親子で取り組んでいきたい方にお勧めです。
さて、ここからはもう少し詳しく「苦手な問題を塾の先生に相談したら「今はやらなくても大丈夫ですよ!」と言われたら?」というテーマで話を進めていきますね。
小4男児のことについて質問します。
息子は塾へ通っているのですが、先日、塾で四角形の面積の勉強をしました。
基本的な面積は求められるのですが、複雑な形の四角形(四角形がいくつか合わさっていて、区切りながら計算していくようなもの)の面積の求め方がイマイチ分かっていない様子だったので、塾の先生に
「息子は複雑な面積の求め方が分かっていないので、次回もう一度演習をお願いします。」
と言ったところ、
「小5、小6と面積の問題は出てくるので、だんだんわかるようになります。」
と先生に言われました。
そこで質問なのですが、今分かっていないのに、年齢が上がれば分かるようになるものなのでしょうか?
教えて下さい。
算数の図形の応用問題ががイマイチ理解できないので、塾の先生にお願いされ、
「次回、もう1度演習をお願いします」
と。
う~ん、積極的でいいですね!!
でも、先生からは、
「小5でまたやるので別に気にする必要はないですよ」
といった対応。
あららら・・・・
なんだか、出会った問題は逃したくないといったエルムさんの意気込みと塾の先生との温度差を感じるできごと。
きっと、そう思ったから
「今やらなくても大丈夫」って本当なの??
と先生のアドバイスに不信感をおぼえたのかもしれません。
実際に、小5になったらできるようになるのかについては、このあと考えていくとして、まずは塾の先生の発言の真意について考えてみましょう。
今回のように、勉強に対して積極的な行動をする親に対して、どうして
「小5、小6と面積の問題は出てくるので、だんだんわかるようになります。」
とコメントしたのか?
一般的な先生側の心情を予想しますと、この2つが思い浮かびます。
そんなこと、できないよ~!
そんな問題じゃないだろう!
の2つです(^_^)
まずは、1つめは、「そんなこと、できないよ~!」について。
今の塾が集団授業型であれば、「次回もう一度演習をお願いします」なんてお願いされても、困っちゃう。
だって、次回のカリキュラムも決まってますから。
クラスの生徒みんなが躓いている問題なんかですと、その問題だけを再度演習なんてことは考えられますけどね。
それも、「基本」「標準」「発展」という段階でいえば、やってくれるとしても、標準レベル問題まででしょう。
発展問題ができないからといって授業で再度取り扱うことは基本的にないはずです。
集団授業において、1人の生徒のために「はい、いいですよ」なんてカンタンに承諾することはできないのです。
塾の規模が大きくなればなるほど、先生の裁量で授業内容を決めるのは難しくなることも知っておくべきでしょう。
逆の言い方でいえば、そうやってきっちりというか、強引にでもカリキュラムを進むことが大事であることも知っておいてください。
よく生徒のレベルに合わせて進むというフレーズが使われるわけですが、ストロングの経験上、生徒のペースに合わせて進んで良かったためしはほとんどありません。
子供にとって1つ上のものをやるからレベルアップするのであって、生徒の今に合わせて進んでいては進歩がありませんから。
中学受験や難関私立高校の受験などのレベルの高い、かつ、膨大な量の勉強を一定の期限までにこなさないといけないものは特にです。
それらを踏まえたうえで、今回の場合でしたら、やはり、お願いをするならば、やはり個人的にお願いをするしかありません。
そして、その場合は、相手に極力負担をかけないフリをすること。
いいですね、「フリ」ですよ(^_^)
例えば、
「この手の問題がイマイチなので、類題を何問かいただけませんか?」
とお願いするわけです。
授業で補ってください!というお願いではなく、あくまでも家で演習させたいので、プリントをください!という感じです。
これなら、先生は問題を準備するだけ(^ε^)-☆
「はい、わかりました」
となれば、こっちのもの。
親切な先生だったら解答もくれるかもしれませんが、できれば欲しくありません(≧◇≦)
で、
「問題を家でやらせるので、答え合わせだけお願いしたいのですが」
とこう畳み込んでいくわけです。
「あっ、はい」
こうくれば、あとはできない問題は「先生、この問題わかりませんでした」と質問できるわけです。
いつも言っていることですが、「お願い」する場合、くれぐれも、言ったこと、約束したことは、キッチリやらせる親だなという印象を持ってもらうことが大事です。
一方的なお願いは意味がありませんから。
お願いして、約束して、それをやってこそ、次につながるわけですからね。
もし個別指導であれば、話は反対で、進度は自分で決めることができますので、気が済むまで演習を繰り返すことだってできます。
ただし、その分そのあとはペースを上げることも忘れないことです。
つまり、塾の先生の事情も考えて、お願いをしないといけないワケです(^_^)
さて、続いて、先生側の心情を予想の2つめ、
「そんな問題じゃないだろう!」について。
今、お子さんの勉強を側でいつも見ていらっしゃるでしょうから、以下の点については、該当しないと思いますが、非常によくある例なので、話をしておきます。
親から相談やお願いをされたとき、先生が
そんな問題じゃないだろう!
こんな風に思うことってよくあります。
つまり「違うやろ!」とツッコミを入れたくなるとき(^_^)
どういうことか?
例えば、基本問題も理解できてないのに、
「うちの子、どうも応用力が苦手なんです」
と真剣な面持ちで相談に来られたとき。
「そんな問題ちゃうやろ!」
塾の先生にこんな風に思われてしまうのは、非常にマイナスです。先生は「そんな問題ちゃうやろ!」と言いたいのですが、お客さんにそうハッキリとは言えないものです(^_^)
そんなときには、
「今はやらなくても大丈夫ですよ!」
といったコメントになるだということも知っておいてほしいものです。つまり、積極的にお願いしたけど、塾の先生からは、子供の状況を把握できてない親というレッテルを貼られることになります。
せっかく、相談に行っても墓穴を掘ることになりますから(>_<)
逆に、的を得た相談をしに来た親ですと、「こっちもしっかり指導せねば」といった良いプレッシャーを与えることになる。
「わかる親」には、しっかりと期待に応えた指導をすれば「感謝される」ということを先生たちは知っていますから。
以上、先生側の心情から考えてみました。
さて、今回の相談の場合は、最初に書いた個別で対応してもらうことで対応してもらう道を選択されたらいいでしょう。
同じ月謝でも親の対応、もっていき方で子供の面倒見も全然違ってきますので、ぜひ親技を発揮してほしいところです。
さて、最後に、
今分かっていないのに、年齢が上がれば分かるようになるものなのでしょうか?
について、書いておきます。
答えは、
そんなこともあります!
なんですね。
極端な例ですが、親が今子供の勉強をそばでみれば、テキストの最初にある例題がなぜそこにあるのか?について、よく理解できると思うのです。
よく問題を読んでみなさい! 親はみなそう言います。
だって、問題にヒントが書いてあるから!
でも、子供には伝わらない・・・・
わからない!と問題を読む前に言う。
ですよね?
昔、難しいと思っていた問題が今なら当時よりもちゃんと意図を理解して納得できたりとかする。
これって、なにかを猛勉強したから昔よりも良くわかるわけではなく、大人になっていく時間の経過の中で誰でもなるものです。
できなかった問題は、できないのが普通なんですが、時間が経つとサラッと理解できることがあるのは事実です。
これは、カンタンにいえば、その後の単元を勉強することで、「あ~、あれと同じやな」と自分なりに収まりがつくから起こる現象です。
大人が子供よりも理解力があるのは、時間の経過の中での経験の蓄積や知識の貯金ができ、知っていることが多くなった結果です。
だから、子供でも、のちにやったら、サラサラできるという事実は現にあるわけです。
それと、精神的な問題もあります。
図形、嫌い!!!
こうなっちゃうと、頭の思考回路がストップして、できてた問題ですらできなくなってしまう。
そうなったら?
これも何度か書きましたが、
理解する→できる・解ける
という道筋が労力から考えても、効率から考えても理想なわけですが、理解できないなら、とりあえず暗記しちゃう。
もちろん、答えだけではなく、途中の式もまとめて。
これは、
できる・解ける→理解する
というように理想の道筋とは逆になってしまうわけですが、それをやっておいて、時間の経過とともに、「あーー、そういうことか」となるようにしてもいいのです。
これもさっき書いた蓄積の1つですから。
暗記するのもイヤって!?
そうれなら、それぐらいだったら、もう一旦やめちゃうわけです。
別に、来年まで待つ必要もなく、長期の休みなどに再チャレンジする。
基本的な事項だけは押さえておいて、先延ばしする。
今日は調子いいなと思ったら、そっと差し出しチャレンジするのもいいでしょう。
こうやって、親が管理することでどこまで押さえるかのタイミングを見て、ここぞと思うタイミングで子供の頭に収めてやる。
これが、「親技」なんですな!
えっ、タイミングが難しいって!?
はい、難しいですよ、非常にね(^_^)
大切なのは、止める基準だと思うのですが、
嫌いにならない程度
を意識することです。
蓄積を優先してガンガンやらせるのはいいのですが、母ちゃんとはもう一緒に勉強しない!なんて言われたら、子供の頭にきちんと収める機会を永遠に失うわけですから。
えっ、キライにならない程度といっても、全部キライで、それじゃあ勉強が進まないって!?
・・・・・・・・
そういわれても、ヤッパリ言えるのは、
嫌いにならない程度
あえて言うなら、子供の今の現状よりは1段階上で、全部をやるわけじゃない!
できる問題から入って、その上で取り組むわけです。
まあ、勢いをつけるわけですな。
そういう意味で、「子供の現状」「好き嫌い」なんかをしっかり把握している人が必ずいる。
特に中学受験では!
しっかりとトライ&エラーしてくださいね!

子どもの頑張りはそのままで、親の工夫や頑張りで成績を上げるノウハウを「親技(おやわざ)」といいます。勉強に関する様々な悩みを子ども任せにせず、親子で取り組んでいきたい方にお勧めです。