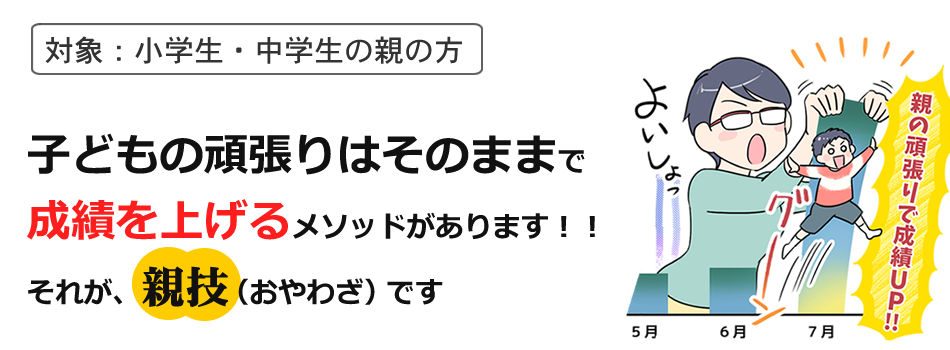「今の子供に合った「考えさせる」と「説明してやる」のバランスを意識する」
算数の力をつける上では、思考力を養うことが大切です。
だからといって考えさせることばかりに重きを置いていては勉強は進みません。
子どもの様子を見て、適度に説明をしてやることで、考えることを促す場合もあります。
大切なのは、親が、今の子供に合った「考えさせる」と「説明してやる」のバランスを意識することなのです。

子どもの頑張りはそのままで、親の工夫や頑張りで成績を上げるノウハウを「親技(おやわざ)」といいます。勉強に関する様々な悩みを子ども任せにせず、親子で取り組んでいきたい方にお勧めです。
さて、ここからはもう少し詳しく「算数の力をつけるためには・・・?」というテーマで話を進めていきますね。
小1の娘のことでこの度質問させていただこうと思ったのは、就学前の子供に養わせたい「数の概念」についての話です。
数の概念は、なにも就学前の子供にだけ必要な話ではなく、今後も大切な話だと思うからです。事実、私にはそういう数の概念といいますか、数字が体感的に理解できておらず、時速30kmというのがどのくらい早いのかも判りませんし、ここからあの標識まで何メートルあるのか、というのもイマイチわかりません。50gといわれてもピンときません。(ちなみに理系人間の主人はそれがすべて一瞬で体感的にわかるようですが…)
ですので、私としては、自分にはないその「数の概念」を娘には体得させたくて、入学前までの間に、お勧めいただいた小学受験用の問題集をいくつか買ってきてやらせたり、卵のパックを集めて、そこにビー玉を入れて、5のかたまり、10のかたまりを意識させたり、今はそろばんに通わせて、数の視覚化を意識させてきましたが、どうもイマイチ体感的に判っていない様に思えてきました。
逆にプリント修練ばかりで、計算マシーン化してしまってる? と心配になってきたのです。
そこで知ったのが、AERA with kidsの小冊子についていました「どんぐり倶楽部」という団体で行っている勉強方法です。
絵コンテ読解というやり方です。
数を視覚化する、という方法論については、私自身が求めてきた方法そのものだったので、まさに渡りに船! と言う感じでさっそく教材を注文してみましたが、そのやり方についてお聞きしたいのです。
先生が以前、「子どもには理屈を教えるよりもまずやり方を教えた方がよい」とおっしゃっていて、私もそのとおりだと思っています。
数をこなしていくうちに、ある日突然、「ママ、繰り上がりってこういうことだったんだね!」と判ってくれた実績もあります。
ですので娘が問題を前にして固まっている場合は、まず解き方を教えてしまいます。そして娘は一度教えると類似問題の場合はそのやり方に従ってきちんと解くことができるのです。
ですが、このどんぐり倶楽部では、それは考える力を削いでしまうからよくない、というのです。
問題をそのまま図にする、というのはいいと思うのですが、何も知らない子どもにこの図を書け、というのは私には難しいように思うのです。
年長さんや小1の場合は、絵を描くのが楽しくなればそれでいい、問題は解けなくても可、といっていますが、それはどうなんでしょうか?
娘の場合、解けないと「自分は馬鹿なんだ…」と思ってしまうタイプだからです。
ですから、自分は出来ない子だと思って欲しくないので、本人が自力で解けるまで毎回必死に付き合ってます。(お陰で仕事も滞ったり睡眠時間削られてます…(苦笑)
本来なら筋違いの質問だとは思いますが、以前数の概念のことで先生からは的確なアドバイスをいただけておりましたので、是非再度的確なご助言をいただけたらと思い、質問させていただいた次第です。
まずは、ご存知かと思いますが、話の性質上、「数の概念」について簡単に説明しますね。
「数の概念」とは、数の総括的・概括的な意味のこと。
???ですか。
簡単にいえば、「数っていったい何?」ってことを知ることなんですが、私たちは就学前にいろいろな遊びを通じて、数の概念を体得することを勧めています。
たとえば、
りんごが10個あるのを2人で分けると何個になる?
といった問題があるとします。
割り算ですれば、「10÷2」なんですが、算術は使いません。
おはじきを使ったり、絵を描いたりすることで答えを導くのです。
えっ、時間がかかるって!?
確かにそうなんですが、時間よりも正確に答えを導き出すことを優先します。
それにこのやり方だと割り算を知らなくてもできるでしょう?
計算の仕方そのものではなく、そこがつまり「数の概念」のところです。
数をかぞえて答えを導くことで、計算間違いの心配も少なく、正確に、そして、答えを出すことができます。
では、こんな問題はどうでしょう?
りんごが10個あるのを3人で分けると何個になる?
もし、割り算で考えるなら「10÷3=3あまり1」となります。
余りのある割り算ですね。
ということは、先の例で出した「10÷2=5」よりかは難易度の高い問題になります。
でも、おはじきを使えば問題のレベルは変わりません!!
3人に順番にりんごを分けるだけです。
配り終えると、結果が答えとなるわけですから(^_^)
おはじきだけでなく絵を描いたりすることで、数を視覚化する。視覚化して問題を捉える習慣は、文章問題などの式を立てる際に役立ちます。
よく、わからないときは図を書いて考えることといいますが、まさにアレです。
さて、少し前おきが長くなりましたが、「数の概念」というものがどういうものかは、なんとなくわかっていただけたと思うので、本題に入りましょう!
相談者さんは、数を視覚化するという方法論(絵を描いて解いてみよう!)をお子さんに実践しようと「絵コンテ読解」というものを試してみたと。
絵コンテ読解とは、どんぐり倶楽部を主催している糸山さんが推奨されているやり方で、絵を書くことで問題の意味を捉え、解答を導く方法を推奨されています。
私も拝見したことがありますが、とても共感できるものでした。
賢い子は頭が柔らかいと言いますが、まさにこんな思考回路なんだよなと思えるものです。
しかも、子供たちが描いた絵を見ると、なんだか楽しそうに問題を解いているのがわかります。
難問を楽しんで解く!まさに理想です。
赤で添削されているのは、糸山さんなんでしょうか?
とすれば、糸山先生もノリがイイですねえ!
イイこと尽くめ!!
ただ相談者さんが言われるように、子供自身が絵を描いて考えることに難色を示した場合にどうするか?
ここですね。これは相談者さんだけでなく、多くの方が経験されているでしょう。
「ウチの子、図や絵を書けって言っても書かないんです!!」
というわけです。
子供に絵を描いて解くことの楽しさを教えてやれればいいのですが、抵抗することだってあります。
現に、相談者さんの場合は、解けないと「自分は馬鹿なんだ…」と思ってしまうとか・・・・・
この状態で無理に「絵を描いて考えてごらん」と勧めるのは逆効果にもなります。
図を書いて考えることは、わかりやすくするため、問題を整理するために行うわけですが、図のイメージが湧かない子にとっては反対に混乱を招いてしまうことがあります。
そんな場合、私は「解き方を説明してやればいい!」と思うのです。
その際に意識してほしいのは、
「考えさせる」と「説明してやる」のバランス
なのです。
子供にはいろいろなタイプがあります。イイ教材でも、イイ塾でも、イイ先生でも、子供によって、向き不向きがあるのは当然のこと。
「イイ○○」だからと、それに子供を合わさせようとするのは、子供も苦しいけど、それに付き合う親もまた苦しい。
なので、親は「理想」と「現実」のバランスを取りながら進める必要があるわけです。親技ですなあ!
では、そのバランスをどう取るか?
例えば、
考えさせる100 : 説明してやる0
ヒントもなしに自分で考えさせる。
これって思考力を養うには、理想です。これにはまる子供はそれでよろしい。
しかし、こうすることで、子供自身のやる気を失せてしまっては元も子もありません。
さきほどの解答用紙なんですが、わが子がこんな風に絵を描くことに難色を示した場合はどうするか?
ちっとも書こうとしない場合、どうするか?
23×3=6969+88=1574710÷157=3030×3=90
これだけ親が書いてやって、この式がどういう意味かを尋ねたらいい!
そう、「ヒント」を出したらイイと言っているわけです。
そのヒントとして、例えば、式を先に示してやり、式の立て方について考えさせるわけです。
そうなると、さっきの
考えさせる100 : 説明してやる0
これが、ちょびバランスが変わって、
考えさせる50 : 説明してやる50
これくらいの比率になりますかね? まあ、だいたいです。
ヒントは出しても、全部を説明するわけではありません。教え込むわけでもありません。
ただ式を示して、その意味を考えさせるわけですから。
だから、思考力だって養うことになります。
「ええーーと、これは・・・・わかった!」そうなれば、OKです。
もし、それでもわからなかったら・・・・・
そのときは、「23×3=69」の式の意味を説明してやります。
こうなると比率は、
考えさせる30 : 説明してやる70
ぐらいになりますかね?
もちろん、これだって思考力は養えます!
えっ、それでもダメ!?
じゃあ、話を分かりやすくするために、極端な話をしましょう。
考えさせる0 : 説明してやる100
こんなになっちゃった!?
さすがにこれでは、思考力は養えないのか?
いいえ! これだって、思考力は養えると断言できるます!
数をこなしていくうちに、ある日突然、「ママ、繰り上がりってこういうことだったんだね!」と判ってくれた実績もあります。
これって思考力を養っていることでしょう?
確かに、「考えさせる」の比率が大きいほど思考力を養うことはできるでしょう。
だからといって、子供がやりたがらないのでは意味はありません。
親は、今の子供に合った「考えさせる」と「説明してやる」のバランスを意識することです。
相談者さんも、ぜひそこを意識してやられたらいいですね。
最後に、相談者さんのメールにあった
先生が以前、「子どもには理屈を教えるよりもまずやり方を教えた方がよい」とおっしゃっていて
この部分について、ちょびコメントしておきます。
これは半分だけ本当で、半分は相談者さんの誤解です。
どういうことか?
私たちが教えるときは、必ず理屈から入ります。
問題集でも、塾のテキストなんかでも、そうなっていると思います。
例題や考え方というのは、「なぜそうなるのか?」という理屈を考える部分ですよね。
その上で、だから、こういうやり方が便利ですよという公式や解法が書いてある。
テストなんかで問題を解く際には、公式や解法を使って解きにかかる。
だからといって、考え方や「なぜそうなるのか?」をすっ飛ばして、やり方だけ教えるわけではないのです。
繰り返しますが、私たちも指導する際には、必ず理屈から入ります。
だって、理屈がわかっていたほうがお得ですから!
どんなお得があるかというと、
- 子供がラク!
- 応用が利く!
- 忘れにくい!
- 公式や解法を忘れても、問題が解ける!
なので、子供にも理屈から指導するわけです。
ただし、子供によっては、理屈がうまく飲み込めない、消化できない、イメージできないことだって多々あるのです。
じゃあ、そのときどうするのか?
根性入れて、繰り返し繰り返し理屈を説明し続けるのか?
答えはノーです。
そのとき、理屈が体得できなかったら、立ち止まらずに、やり方を教えてあげる。
理屈がわからなくても、公式や解法、つまり、やり方がわかれば問題が解ける場合も多くありますから。
「なーーんだ! 小難しい説明はわかんなっかったけど、この問題カンタンやね!」
こういう気分=ノリノリにさせてやる。そしたら、何が起こるか?
「問題が解ける!」という気分にしてやって、そのあとに理屈がわかるということが起きるのです。
「あー、わかった!」というやつです。
相談者さんの
数をこなしていくうちに、ある日突然、「ママ、繰り上がりってこういうことだったんだね!」と判ってくれた実績もあります。
これなんかは、まさにその典型でしょう。
つまり、
理屈→やり方やり方→理屈
どちらの道筋かは、こだわらずにやったらイイ。
理想はありますよ。でも、理想が現実に合わない場合もあるのです。
そのとき、「我が子はアホ!」と決め付けてほしくありません。アプローチを変えることでわかることだってあるのですから。
くれぐれもなんでもかんでも理屈はほっておいて、やり方を教えなさい!と言っているわけではありませんからね!

子どもの頑張りはそのままで、親の工夫や頑張りで成績を上げるノウハウを「親技(おやわざ)」といいます。勉強に関する様々な悩みを子ども任せにせず、親子で取り組んでいきたい方にお勧めです。